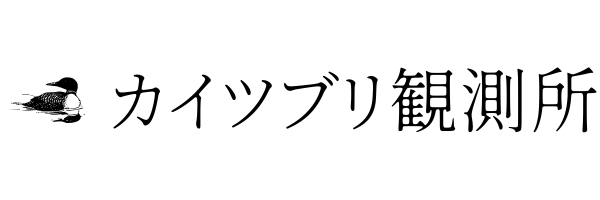そこに愛があるのなら
ゼルダは旅から帰ると、すぐその植物を鉢に移しかえた。
家にあるものではもっとも小ぶりな鉢だったが、それは親指の腹ほどの大きさでしかなかったので、十分に足りた。
たっぷりと土を敷き詰めたあと、その中心に株を慎重に埋めた。
「あるべき土地から移すのは、本当は良くないことなのですけれど。どうしても、これは手元で観察したくて」
と、ゼルダは言った。
鉢はベッドサイドに置いた。
砂漠の生き物だから、水も栄養もほとんどいらない。たまに、匙一杯の水で湿らせるだけでいい。
ただ、日光だけは欠かしてはいけない。確かにそこは日当たりのいい場所で、うまくいけば、朝日がのぼってから午後の半ばまで陽光がとどいた。
それはいつ見ても、不思議な形をしていた。
ゲルド砂漠の奥の奥、流砂のたまり場のような化石群で見たとき、リンクははじめ、それが植物、大きな括りでいえば生き物なのだとは分からなかった。化石たちの根元にぽつぽつと生えているそのさまは、リンクが想像する植物とは、あまりにも異なっていた。
化石の中から漏れた何らかの物質の固まりだと言われたほうが、ずっと納得がいく。あるいは、新種の魔物。
実際、ハイラル各地に出没する魔物であるチュチュのような特徴を持っている。緑色で半透明。触ってみると、ゼラチン質のぷよぷよとした弾力が返ってくる。
果実のように丸い形をしているが、他の植物でいえば葉に相当する部分らしい。
「砂漠は、生き物にとって過酷な土地ですからね。これは体のほとんどを地中に埋めて、貴重な水分を蓄えるの。でも、完全に潜ってしまうと光合成が出来ない。だからごく一部を地表に出して、そこを半透明にすることで、地中に太陽光を透過させて栄養素を生成しているの」
ゼルダは丁寧に説明してくれたが、それがどれほど大変なことなのか、理解できたとは言いがたい。
ただとにかく、これが見た目に違わずとても珍しく、多様な生物が生きるハイラルの中でもかなり変わった部類ものだということは、リンクにも分かった。
ゼルダがどうしてこれを持ち帰ってきたのかをリンクに教えてくれたのは、二か月ほどが過ぎたあとだった。
「あのころ学者たちのあいだで、これをめぐって、ちょっとした論争があって」
あたたかな素足をリンクのそれに絡めながら、ゼルダは言った。
月が出ていて、青白い光が窓枠を照らしていた。季節は秋の入り口に来ていた。
「ある学者が、こう主張したの。これに類似する植物はハイラル中のどこにでも存在するけれど、こんな形質をもっているのは、砂漠下で生きるこの品種だけだ。これはつまり、過酷な環境で生き延びるために、生物が長い時間をかけて自ら変化した結果だ、と」
ゼルダの指が、リンクの胸筋の継ぎ目をなぞっていく。
リンクは聞いた。
「長いって、百年くらい?」
「まさか」
ゼルダは笑った。
「その学者は、十万年ほどだと試算していました」
十万年。
ずいぶんと、気の長い話だ。
「私はその説を信じていません。証拠もないし、類例もない。でも、突拍子もない思いつきに突き動かされた学者の与太話だと切って捨てるには、あまりにも魅力的だから」
「魅力的かな」
「ええ、とても」
雲が出てきたのか、単に夜が深くなったのか。気がつくと、部屋はほとんど闇に沈んでいた。
あの植物は鉢植えの中で、夜をどのように見つめているのだろうと、リンクは思った。暗くて何も見えないのだろうか。それとも、全身で受け止める月の光の眩しさに震えているのだろうか。
ゼルダは言った。
「百年ぶりにあれを見て、こんなことを思ったの。もし本当に、十万年、この種が生きているのなら。このハイラルが、十万年、……いいえ、それ以上の歴史を持っているのだとしたら。そのあいだに、いったい何度厄災があらわれたのだろう。そのたび姫巫女と勇者が顕れて、封じて、また復活しては封じて。繰り返し繰り返し。生物が形を変えて、透明な身体を手に入れるほどの時間を、延々と、果てることなく」
ゼルダの言葉は、夜のすき間を埋めるように流れていった。
リンクはゼルダの背を撫でた。背骨が列をなし、整然と並んでいる。そのさまを確かめるのが好きだった。
「そしてこれからも、それは続くのかしら。一万年、十万年、百万年」
しっとりとした粘膜が、肋骨と肋骨のすき間に押し当てられる。ゼルダの唇は、不思議といつでも湿っていた。
「その頃にはもう、厄災は跡形もなく滅び去っているのかしら。女神の血はとっくに絶えていて、勇者の魂も、役割を全うして天に還っているのかしら」
この世界が厄災に見舞われるたびに顕現する、勇者の魂と女神の血を継ぐ姫巫女。
女神が定めたこの世のことわり、もしくは呪い。
リンクとゼルダ。
リンクは想像してみた。
ずっとずっと遠い未来。
ハイラルは変わっているのかもしれない。緑豊かな平原も、険しい岩山も、真っ白な雪原も、一面の砂漠も、どこにもなくなっているのかもしれない。
そこに人が住み続けていたとして、その姿かたちも、想像もできないようなものに変わっているのかもしれない。
それこそあの植物のように、半透明な身体をもっているのかもしれない。
二つの目は三つになり、鼻はなく、かつての名残りのように細い骨だけを残しているかもしれない。
耳は頭蓋と同化しているかもしれないし、口は音を出したり栄養を取る以外の用途に使われているかもしれない。
それでも、とリンクは思う。
「なにも変わらないよ」
リンクはゼルダの肢体を抱き寄せた。
身体と身体のあいだで、豊かなふたつの乳房がつぶれて歪んだ。たまらないというようにこぼれたゼルダの喘ぎ声が、耳の中で反響する。
どんな姿になろうとも、リンクはゼルダの側にあるのだろう。
そしてそこに、たとえば自分たちが愛と呼ぶような歓びがあるのなら、今この瞬間にいる自分たちと、いったいなにが違うのだろう。
ゼルダの頬を両手で包み、真っすぐに見据える。
透き通った緑色の両目。すんなりとした鼻筋、長い耳、肉の厚い唇。
「変わらない」
リンクは繰り返した。
転生、魂の循環、輪廻、宿命。
言いようはさまざまにあるだろうが、リンクがなすべきことは、いつでも一つだ。
「俺はゼルダの側にいる。だから、なにも変わらない」
「そうね」
ゼルダは笑った。
「きっと、そう」
十万年の向こう側を夢見るように、ゼルダは細く細く息を吐き、そっと目を閉じた。
〈了〉