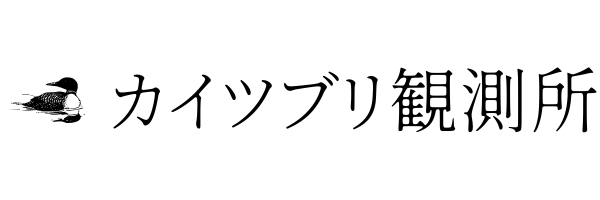虹の彼方に
さあ出発、という時になって、雨が降ってきた。
夜と朝とが入れ替わる、その瞬間を狙いすましたかのようだった。雨粒は細く、空は比較的明るい灰色をしている。長くは降らないだろうという予感はあったが、しかし、出足をくじかれたことに変わりはない。
私は小さくため息をついて、馬宿の入り口から、中へと戻った。
つい一時間前まで横になっていたベッドに腰かける。
宿泊は今朝までの契約で、正確にはもうこれを使う権利は私にはないが、他に適当な場所が思いつかなかった。
「にわか雨ですよ。なに、ここいらではよくあることです。すぐに止みますから」
宿の主が、他の旅人に説明しているのが聞こえる。
このあたりは、巨大な活火山であるデスマウンテンの山沿いにあたる。
山の斜面で発生する上昇気流は、雨雲を作り出す。だから、急な雷雨に見舞われやすい。
私は腰のポシェットから、手帳を取り出した。
特に目的があるわけではなかったが、ぼんやりと時間を過ごすよりはいいだろう、というくらいの思い付きだった。ぺらぺらとページをめくる。右肩上がりの癖の強い私の字が。紙面の大半を埋めていた。そこにときどき、気になった動植物の写生や、各地に残る遺構に彫られた意匠の書き写しが混じっている。
我ながら、よく旅をしていると思う。もちろんそれは、ずっと側にいてくれるリンクも同じだ。
と、横から声をかけられた。
「おとなり、いい?」
舌ったらずな、愛らしい申し出だった。私はすぐに返事をした。
「どうぞ」
「ありがと」
シャーメ嬢はにっこりと笑って、ベッドによじ登ってきた。
宿の主人の一人娘だ。
ここに滞在したのは約一週間だったが、そのあいだに、随分と懐いてくれた。このあいだ六歳になったから、シャーメ、もうお姉さんなの。そう胸を張って自慢していたのは、おとといの夕食時だったか。リンクが頭を撫でようとすると、お子ちゃまじゃないもん、と頬を膨らませていた。
「お絵描きですか」
「うん」
シャーメ嬢はベッドに紙を広げ、這うような恰好で絵を描き始めた。
手にしているのは子どもたちが書きものによく使う、顔料を混ぜた蜜蝋だ。棒状で、先端以外は薄紙を巻いてある。握るときに、手に油分が付かないための工夫だ。
赤、黄、オレンジ、緑、くすんだ茶色に黒と白。それだけの色ではどれほど望むものが描けるのだろうと思ってしまうが、シャーメ嬢はちっとも気にしていないようだった。
「にじーのむこうーにはー、なにーがあーるのー」
即興であろうを歌を口ずさみ、ご機嫌に身体を揺らしている。
緑色の三角形がいくつも並び、端のほうに、黒で塗りつぶされた直線的な造形物がある。そしてそれらを渡っていく橋のように、大きな曲線が掛けられている。
曲線にはすべての色が使われていて、いくつもの層をなしていた。赤の次に緑、黒の下に白とオレンジ。配色は別として、それが虹を表しているということは、すぐに分かった。
「ここから見える景色ですね」
「そうよ」
シャーメ嬢は手を止めずに言った。
「お日さまがのぼるとね、お山に虹がかかるのよ」
あ、そうだ。お日さま忘れてた。そう言って、シャーメ嬢は虹のアーチの真下に、黄色でぐるぐると円を描いた。
私は彼女の邪魔にならないように注意しながら、そっと紙面に触れた。
ざらりとした感触が指に残る。繊維が残っていて、紙としての品質は高くない。しかし百年前の厄災で高度な技術が潰えた現在のハイラルでは、ごく一般的なものだった。
やがてシャーメ嬢は、緑の三角形の一辺を丁寧に塗り始めた。
虹のアーチの終点、おそらくは山の裾野であろうそこを、黄色やオレンジといった、目立って明るい色で彩色していく。
「そこは?」
と聞くと、シャーメ嬢は顔を上げた。
「”おたから”よ」
「”おたから”?」
よくぞ聞いてくれましたとばかりに、シャーメ嬢は首を縦に振った。ふくよかな頬が、嬉しそうに緩んでいる。
「前にね、旅のひとから聞いたの。虹の根っこには、”おたから”が埋まってるんだって」
そう言っているあいだにも、紙は色を増していく。蝋が光を反射して、本当にそこが輝いているかのようだった。
「シャーメね、考えたの。どうして虹の根っこに”おたから”があるんだろうって。それでね、きっとそれって、お空の国のものなんじゃないかなって。お空の国の”おたから”が、虹をつたって落ちくるの。だからきっと、虹の根っこって、すっごくきらきらしてるはずなのよ」
「お宝がなんだって?」
気がつくと、目の間にリンクが立っていた。
「面白そうな話をしてる」
リンクは興味津々というように、シャーメ嬢の作品を覗き込んだ。
旅費の足しにと余分な素材を行商人に売りに行っていたのだが、交渉は首尾よく終わったようだ。表情を見れば、だいたいのことは分かるようになった。
「おにいちゃんもシャーメのお話、聞く?」
「聞かせて」
そう言ってしゃがみ込んだリンクに、シャーメ嬢はふたたび説明をはじめた。
山々の上に広がる青い空に、太陽と、大きな大きな虹の橋。そこには、いい子にだけは見える国がある。そこにはたくさんの”おたから”があって、それは虹の橋を滑り落ち、やがて地面にたどり着く。だから虹の向こうはきっと、まばゆいほどに光り輝いているはずで――。
「雨が上がったぞ」
外の様子を見ていた旅人が、声を張った。
それを機に、宿の中で待機していた人々が一人、また一人と入り口に向かっていく。
シャーメ嬢もまた、ぱっと身体を起こしてベッドを降りた。駆け足で外に飛び出したかと思うと、きょろきょろと周囲を見回す。やがてなにごとかに驚いたように小さく飛び跳ねて、その勢いのまま、ふたたび私たちの側に帰ってきた。
「虹だよ!すっごいの!早くきて!」
興奮に頬を赤くしながら、シャーメ嬢は叫んだ。居ても立っても居られないというように、リンクの肩を掴んで揺する。
「分かった、分かった」
リンクは左右に振られつつ、さっと立ち上がった。ゼルダはゆっくりでいいよ。そう言い残し、飛び出していったシャーメ嬢の後を追う。
ベッドには私と、未完成の絵だけが残った。
私はあちこちに散らばったままの画材を紙の脇にまとめながら、あらためてそれを見つめた。
この絵には、いくつか間違いがある。
まず、虹の配色が違う。外郭から順に、赤、オレンジ、黄色、緑と並ぶべきで、二種の青と紫が足りない。
また、太陽と虹は同じ方向に現れることはない。
虹は空中にある水滴と太陽光とが起こす、光学的な現象だ。
それは観察者の背中側、つまり虹と反対側にの空に太陽があるときにしか成立しないことは、よく知られている。
そして、虹に根元はない。
虹の一端が現実にあるもの、たとえば大木や建築物などと接していると、いかにもそこが虹の始点、あるいは終点のように感じられる。しかし実際にそこに向かおうとすると、観察者が移動するのにあわせて、虹も移動してしまう。
虹はあくまでも現象であって、私たちがそれを手にすることは、永遠にかなわない。
「おねーちゃんも!早くー!」
大声で呼ばれ、私はゆっくりと腰を上げた。雨水を含んだままの幔幕を出て、空を見上げる。
見事な虹がかかっていた。
それは目に見えるだけの景色のすべてを繋げてしまうのではないかと思えるほどに大きく、雄大だった。
すぐそこにあるゴングルの丘をはるかに飛び越え、向かって右、方角にすると北側に黒くそびえ立つハイラル城の影を起点とし、左方はナリシャ高地――いや、ラネール台地にも届いているだろうか。あまりにも大きすぎて、正確なところは分からない。
シャーメ嬢の手が、私の袖に飛びついてきた。
「見て見て!”おたから”!」
小さくやわらかな指が、はるか遠くを指し示す。
「きらきらしてるでしょ?ね、ね!」
私はよくよくその先、虹と大地とが重なり合う一点を確かめようと、目を細めた。
しかしそこには白っぽく霞む山々と抜けるような空とがあるだけで、シャーメ嬢の言うような輝きは見当たらない。その目にはいったい、何が映っているのだろう。
「ラネール参道の方かな」
すぐ横で、リンクが言った。
「確かに、妙に明るいな。何かあるかもしれない」
「ほんとう?」
「”おたから”かどうかは、行ってみないと分からないけど」
リンクがそう言うと、きゃっ、とシャーメ嬢は手を叩く。私は思わずリンクを見つめた。
「どうかした?」
陽光の中でひときわ明るさを増した青い目が、不思議そうに私を見返してくる。
「……いいえ」
私は首を振った。
彼が、例えいっとき子どもの機嫌を取るためであっても、適当な嘘を言うような人でないことは、他ならぬ私が一番に知っている。それに、表情を見ればちゃんと分かる。
きっと彼には本当に、何かが見えたのだ。
「そろそろ出発しましょうか」
「うん」
厩舎から馬たちを出すと、待ちかねたというように首を伸ばし、鼻を擦りつけてきた。私たちよりもずっと、足止めが堪えたらしい。
「今度来たら、”おたから”見せてね。約束よ!」
敷地のぎりぎりまで出てきて見送ってくれたシャーメ嬢と指きりをして、私たちは宿を後にした。
「今日はどうする?」
「そうですね……」
少しだけ迷ったあと、私は言った。
「虹の根元まで、行ってみましょうか。”おたから”を探しに」
えっ、とリンクが声を上げた。
「何それ。どういうこと」
慌てたようなリンクの様子に、私は笑いをかみ殺した。
虹はすでにその色合いを薄くしていたが、まだ空のさなかにある。緩やかなアーチの下を、雁の群れが隊列をなして飛んでいく。
それを見上げながら、私は思う。
虹は決まった色をしているし、太陽と共にはあれないし、掴むこともできない。
それは揺るぐことのない、科学的な事実だ。
でも世界は、それだけで出来ているわけではない。
見えないもの、触れられないもの、理解することの難しいものが、たくさんある。
だからもしかしたら、空には国があるのかもしれない。
虹はそこにかかる橋なのかもしれないし、つたい落ちてきてた宝物たちが、地面で不可思議に光り輝くのかもしれない。
百年前の私には、それが分からなかった。
でも今なら――リンクと一緒の今なら、分かる気がする。そういう気持ちにさせてくれる何かが、この人にはある。
「行きましょう。虹が消えてしまう前に」
そう言って軽く腹を蹴ると、馬は嬉しそうにいななき、その足を速めた。
軽快なリズムに合わせて風景が流れていく。雨あがりにふさわしい、さっぱりとした空気が頬に心地よかった。
このまま、虹の向こうまで駆けていける気がした。
〈了〉