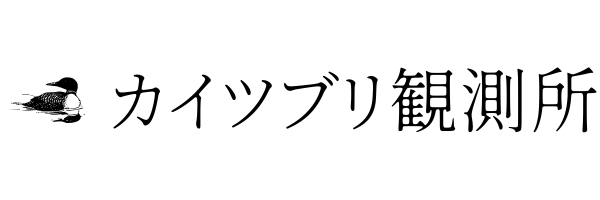雪にあらず花にあらず
いつもと違う匂いがする。
その感覚で、リンクは目が覚めた。
が、同時に外気の冷たさも伝わってきて、あわてて布団の中へと逆戻りする。
カカリコ村の冬は、ハテノ村とはまた違う、底からくるような冷えがある。滞在時に使うようにとインパが手配してくれた家は、手入れが行き届いた素晴らしいものだ。しかしもちろん、寒さを完全に遮断してくれるわけではない。
さらにいえば、この村のベッドは足が短い。床に直接布団を延べるシーカー族の伝統を汲んでいるらしいが、冬を過ごすには不向きな風習だと、リンクはつねづね思っている。雪のある季節に訪れた自分たちが悪いといわれれば、それまでの話だが。
ともあれリンクはその匂いの正体について、寝起きでろくに回らない頭で考えた。
危険を示すもの――たとえば煙、火薬、毒のたぐい――ではない。食べ物、でもない。
そういう、すばやく五感に訴えかけてくる強さはない。
もっと淡くて、どちらかといえば頼りない。空気の中をふわふわと漂いながら、どこかにたどり着けばそれでいいというような気楽さ、あるは余裕がある。知らないものではないはずだが、さほど馴染みがあるわけでもない。
リンクは思い切って、布団の縁から顔を出した。これ以上考えても、埒があきそうになかった。
匂いは寒さにつんと突っ張った鼻の先を、すいとかすめていく。二度、三度と呼吸を繰り返すうちに意識がはっきりとしてきて、それに合わせるように、記憶がゆるゆるとよみがえってくる。
確か同じ季節、寒い時期だった。その時はもっと鮮烈で、華やいだもののように感じた。数が多かったからだ。背の低い枝の先についた、細工物のような赤と白――。
(あれだ)
リンクがそれを思い出したのと、隣で眠っていたゼルダが声を上げたのは、ほとんど一緒だった。
「リンク?」
肌寒さを感じたのか、ゼルダは身じろぎをしながら目を開けた。といっても、意識はまだ夢の中にあるようだった。髪が額に落ちかかっていたが、それを払おうともしない。
「ごめん、寒かった?」
リンクが言うと、ゼルダは緩慢に首を横に振った。しかし熱を求めているのは確かなようで、黙ったまま、もぞもぞとリンクに張り付いてくる。
冬眠中の小動物は、こんなふうに穴倉の中で過ごしているのだろうか。そんなことを想像しつつ、リンクはゼルダの身体を抱いた。まだ十分に温かく、とても柔らかかった。
「インパのところに行くまでに、少し寄り道しよう。梅が咲いてる」
リンクたちが梅園を訪れると、主であるミツは目を丸くした。
「ちょうど今朝がた、一つではございますが、白が花を付けまして。姫さまにご報告をと、ええ、そう思っていた矢先でございます」
梅園はけっして大きくはないが、立派なものだ。赤と白とがそれぞれ十数本程度、命よりも大切だと公言して憚らないミツによって、大切に育てられている。
そのうちの一つから、例の香りがした。
枝には雪が厚く積もっているから、遠目にはまず分からない。が、近くに寄ってみると、いかにも重たげに花びらを垂らしながら、しかし確かにたった一輪、白い花が咲いていた。
感に堪えないとばかりに喜ぶミツと別れて、二人はインパの屋敷に向かった。
「よく分かりましたね。私なんて、かなり近づかないと気がつきませんでした」
ゼルダはいたく感心したようだった。
「そう?」
「だって、花も雪も、ほとんど同じ色なんですもの。香りだって、言われてみればというくらいで」
ラネールやへブラといった寒冷地帯のものと違い、このあたりの雪は水分が多い。道に残るそれを踏みしめると、しゃりしゃりと音がした。
「雪のあるところって、匂いがしないから」
リンクがそう言うと、ゼルダは不思議そうな顔をした。
「雪原に行くとよく分かるよ。あそこは音もしないけど、匂いもほとんどない。多分、生き物がいないからじゃないかな。だから雪ばっかりのところに何かがあると、すごく際立つ。花とか、匂いの強いものは特に」
言いながら、なんだか自分が獣のように思えてきて、リンクは複雑な気持ちになった。
こういう嗅覚は犬や狼に備わっているものであって、文明的な生活を送る人間に必要な能力なのかどうかは、正直疑わしい。
幸いなことに、ゼルダはそこまで思い至ってはいないようだった。リンクの説明に、なるほど、と素直に納得している。
「次に雪原に行くときには、匂いにも気を付けてみますね」
そうして目的地はもう目の前というところまできて、あれ、とリンクは足を止めた。
匂いが、変化している。
リンクは周囲を見回した。日が昇り、ぽつぽつと人が出てきた。藁ぶきの屋根の上で、小鳥が甲高く鳴いている。梅の匂いはそういった諸々に紛れて、もうほとんど消えかかっている。
しかし代わりに、別の香りがする。すぐ近くからだ。
甘いが、押しつけがましくはない。主張はあるものの派手さとは無縁で、人を魅了する、凛とした気品がある。
その出どころは、考えなくてもすぐに分かった。
「どうしました」
「……何でもない」
リンクは手で鼻を覆った。これ以上吸い込んだら、おかしなことになりそうだった。普段は気にならないのに、どうして急に、こんなにも強く感じるのか。
残り香だ、とリンクは思った。
花の香りがかすかに移り、本来のものと混じり合って微細に変化している。そして己の身体は不必要なほど鋭敏に、それを感じ取って反応している。
「インパが待ってますよ。行きましょう」
何も知らないゼルダが笑う。
冷えた空気の中で吐く息はほんのりと白く、頬がかすかに赤い。先ごろ短くした金色の髪が、雪の照り返しを浴びてきらきらと光る。
そこにすぐにでも鼻先を埋めたいという誘惑に、リンクはかろうじて耐えた。それこそ、犬や狼ではないのだ。
「ねえ、ゼルダ」
「はい」
「雪の季節は、家にいよう。寒いし、ほかにも色々と」
「え?」
首を傾げるゼルダを置いて、リンクは足早に歩き出した。
節度と良識ある人間としてあり続けるためには、もう少し、ゼルダとの距離を開けておかなければいけない。
花が咲ききるうちに帰らなければ。リンクは、そう決意した。
〈了〉