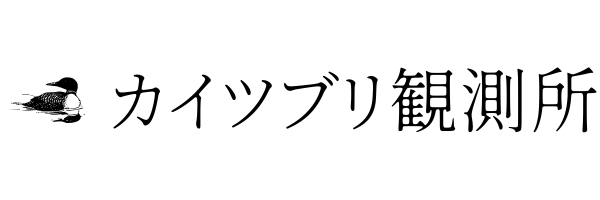今週だけで3回も急な雨に見舞われました。
ありがたいことに分刻みの天気予報のおかげで事なきをえたのですが、これがなかった時代は、人間は空の色を見たり空気の湿り気を感じたり、中には肌の感触、口の中の乾きぐあい、土から立ち上る匂いなんかで雨の気配を感じていたわけで、そういう感覚は使わなくなっていくと段々と薄れていくのかなぁ、などと思いました。
昔の(といって平成初期あたり)小説には、晴れた空を見上げて「そろそろ雨が来るな」とかふいにつぶやくご老人がよくいたものですが、そういった存在のリアリティ(写実性ではなく、いかにもありそう、と感じられるという意味での)が失われつつあるかもしれない。
逆にいえば、そういったものを保持する人は謎の特殊技能として能力バトルで使えたり、魔法体質の異次元生物として面白がられるかもしれない、なんてことをとりとめなく考えたり。
【今週の告知(めいたもの)】
今後のイベント参加予定について、ぼんやりと考えています。
リンゼルでは11月のゼルダオンリーと来年2月のリンゼルオンリー、リベサガでは11月のサガオンリーに出られたらいいな、という感じです。
いちおうどのイベントにも新刊を出せたら御の字ではあるのですが、なにぶん予定は未定なので、そんな気持ちでいるよ、というくらいのお知らせです。
【今週読んだ本】
『「カッコいい」とは何か』(平野啓一郎/講談社現代新書)
最近とある方と「自分はリンクさんはカッコいいと思って書いている(つもりです)のに、なぜモテなさそうなのか」という話で盛り上がり、そもそもカッコイイって何だ?と疑問に思っていたところ、おあつらえ向きにこんな本があったので、とっかかりとして読んでみました。
何より新書の平野啓一郎なら大丈夫だ、という謎の安心感。分人主義の本はとても面白かった。なお小説は句読点の打ち方の癖の強さについていけない自分がいます……。教養本やエッセイだとものすごく読みやすいので、おそらく平野氏は書き言葉(小説)と話し言葉(エッセイなど)を明確に区分していて、その差なのだろうなぁ。
閑話休題。
モテ指南書めいたタイトルのイメージとは裏腹に、ギリシャ~近・現代のカルチャーを俯瞰し、思想・文学・音楽・服飾・それを包括するメディアとの関連などを検証しながら「カッコよさ」を再定義していく内容。平野氏の博学ぶりをここぞとばかりに活かしたジャンル越境的な文化批評で、最後までぐいぐい読んでしまいました。
「カッコイイ」は体感主義(「シビれる」)と強く結びついている、という主張には、思わず我が身を振り返って「あ~~!!」と叫びました。キャラをカッコイイ!って思う時って頭を抱えてうなりませんか私は抱えてうなります(早口)古のオタクはよく「萌え転がる」と表現しましたが、まさに体感そのものって感じですよね……。
あと、「遠くて近い」存在であること。
「自分とは凡そ懸け離れているはずなのに、どこか自分自身のようにも感じられることである」(本文抜粋)
作者は「カッコイイ(しびれる)」に先立つ概念として「恰好がいい(理想に適っている)」という言葉を紹介して、「しびれる」非日常的感覚が「恰好がいい」として日常化する流れを見出していて、ここもなるほど~!と驚きました。
ただここで、その「理想に適っているかどうか」はある程度共有された価値観の元でジャッジされるものなので、それを醸成するメディア(昨今ではネット文化)の影響力に言及していて、往々にして同調圧力が強化され、排他的・先鋭化する問題にも分かる〜となったり。◯◯いいよね→◯◯しか勝たん→◯◯しかいない集団を形成→衰退→何だったんだろうねアレ…はオタクジャンルではよく見る現象。
この本で提示されたアレコレについて、もっと考えてみたいな~と思ったことはたくさんあるので、折に触れて読み返してみようと思っています。
で。
とりあえず大元の「リンクさんはカッコイイはずなのにモテなさそう問題」。
もう一度その方とお話してみたんですが、
「女が好きになるのは”全部が全部カッコイイ”男ではなく、”私にだけカッコイイ”男だから」
という至言をいただきました。
その発想はなかった~~~~~~!!!!!(全部が全部カッコイイ男でないとカッコイイ判定しない人の感想)
ついでにいうとヴィクトール兄さんも全部が全部カッコイイと思っています。そしてモテなさそう。