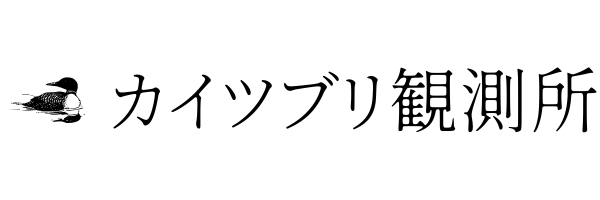そしてLがいなくなった
気がつくと、目の前に扉があった。
リンクの背よりも少し大きい、木製の、何の変哲もない扉。
これを開けろということなのだろうな、とリンクは思った。
周囲は真っ暗で、扉以外には何もない。
扉というからには壁なり建物なりに据え付けられているはずだが、そこには闇があるばかりだ。どう考えても夢だの幻想だのといわれる状況。
(女神さまがまた、変な気まぐれでも起こしたかな)
リンクはため息を吐いた。
この手の突拍子もない事態には、悲しいかな、そこそこ慣れてしまっている。
ドアノブに手を掛けると、意外なほどにしっかりとした手ごたえが返ってきた。
奇妙な現実感。嫌な予感がいや増してくる。
が、ここで突っ立っていても仕方がない。
リンクは覚悟を決めて、扉をゆっくりと押し開いた。
中はホールになっていた。
大きな町の旅館か、そこそこ立派な食事処という感じだろうか。
高い天井、木組みの屋根、漆喰の壁、板張りの床に延べた素朴な柄のカーペット。
造りそのものは、リンクの住むハテノ村にある唯一の宿屋、トンプー亭のそれに近い。
ホールには丸テーブルがいくつも置いてあって、それぞれに椅子が四つ備え付けられている。
壁沿いにスツールをずらりと並べたカウンターがあり、奥には、いかにも雑談に向いていそうな複数人掛けのソファが据えられている。どれも適切に距離が離されていて、ここが居心地のよく過ごせる空間であることは間違いない――そこにいる人間が全員、”自分”でなければ。
ホールにいるおおよそ二十人前後の人間。
椅子に座って飲み食いしている者。うろうろと落ち着きなく身体を動かす者。机に突っ伏して寝こけている者。外の様子が見えないかと窓枠を覗きこんでいる者、ソファの隅に座って、手帳になにごとかを一心に書いている者。
それぞれの見た目には多少の違いがあって、髪が短かったり長かったり、着ているものがシャツだったり鎧だったりぼろぼろのマントだったり、見たこともないようなへんてこな着物だったりはする。
しかし、金色の髪、青い目、長くて先のとがった耳、薄い色の肌、基本的な顔の造形といった特徴は、どれも測ったように一致している。
まぎれもなく、これらすべては自分だった。
「……なんだ、これ」
長い長い沈黙のあとで、リンクはそれだけをつぶやいた。
謎の扉を開けた途端、そこにいる全員の自分の視線が一斉にこちらに向けられたとき、いったいどんな感想を言えというのだろう。
気味が悪い。
いや、意味が分からない。
今まで非現実的な経験はさんざんしてきたつもりだが、こういった方向性は初めてだった。
「あ、新しい俺がきた!」
よく通る、元気な声。見るとカウンターの向こう側で、ひどくラフな格好をした自分が、威勢よく手を振っている。
「こんにちは ……って、こんばんは? かな? まあいっか。こっちで受付していってよ」
「受付?」
雰囲気の異様さにはおよそ似合わない、現実的な単語だ。
だが、相手の自分は気にもしていないらしい。おいでおいで、と人懐っこく手招きをしている。
リンクは念のため、後ろを振り向いた。
想像通り、入ってきたときにはあったはずの扉は、綺麗さっぱりなくなっている。
(しばらくはここにいろ、ってことだな)
リンクは肩を竦めて向き直り、カウンターへと足を向けた。
現時点で取れる行動は、あまり選択肢がなさそうだ。迷っていても始まらない。
第一、いま自分を呼んでいるのは自分だ。そうそう危害を加えられるものではないだろうと、リンクは判断した。
「そこに座ってて。いま水を出すから」
勧められたスツールに座りながら、リンクは目の前にいる自分を観察した。
赤い襟なしの半袖シャツ、頭には木の葉色のバンダナという、分かりやすく活動的ないで立ちをしている。十六、七歳のころの自分によく似ていたが、格好がくだけている分だけ幼く見えた。
「腹減ってない?ここ、キッチンになっててさ。簡単なものなら作れるよ。サンドウィッチとか、串焼き肉とか。他の俺たちも美味しいって褒めてたよ」
「いや、飯はいい」
とりあえず腹は減っていなかったので、申し出はありがたく断った。
そこここのテーブルに出されている料理は、どうもこの自分の手によるものらしい。この状況で、飯を作ろう――そして食べよう――という発想に至った適応力と肚の太さに、リンクは感心した。
もっとも、人一倍、いや三倍ほどは食う我と我が身を振り返れば、なるほど自分らしい行動なのかもしれない。
「ようこそ」
そう言って横から手を差し出してきたのは、ふたつ隣のスツールに座っている自分だ。
こちらはまた、極端に風体が違う。
襟元までぴたりと詰まった、ハイラル王国近衛兵の制服。
今は制帽は外されていて、カウンターに置かれている。横に流した前髪。肘までもある長い手袋の白さが目に痛い。
三十がらみかという年齢と低い声もあいまって、どことなしに風格がある。受付係という役職にはやや仰々しいような気もするが、信頼感という意味では、少なくとも赤シャツよりは上だった。
利き手は自分と同じ左手なのかなと思いつつ、儀礼通りに、リンクは右手で握手をした。
自分と握手をするなどという経験は、ぜひ、これが最初で最後であってほしい。
「せっかくだから、出席簿のようなものをつけたら面白いかなと思ってね。よければ、ここに記入してくれ」
近衛服が、一枚の紙をこちらに寄越してきた。
出席簿という言葉の通り、そこには簡単な一覧表が書かれていた。
項目欄は左から順に、通し番号、名前、所在、職業、となっていて、その下に、ずらっと自分たちの情報が記載されている。これによると、すでに二十二人の自分がここにいる、らしい。
リンクが一番に思ったのは、名前の項目はいらないだろう、ということだった。
全て”リンク”だろうし、実際、そうなっている。
赤シャツが寄って来て、はい、と水を満たしたグラスを置いた。
「俺はこれね。十二番目」
指差した先には、”十二、リンク、ウオトリー村、料理人兼漁師兼狩人兼観光ガイド”と書かれている。職業の紹介としては滅茶苦茶だが、日々をどのように過ごしているのかは、だいたい想像がついた。
「私は四番目だ。ちなみに、一番目は奥のソファで寝ている。途中までは起きていたんだが、考えるのに疲れたから、何かあったら呼んでくれと」
「自由だな」
リンクは憮然とした。
が、もし自分が最初にここに来て、以来延々と訪ねてくる自分を見続けたら、そういう反応をするかもしれない、とも考え直した。
「結構色々あって、わくわくするよね。まあ全部俺なんだけど」
自分自身に出してもらった水を飲みながら、確かに、とリンクは同意する。
ざっと目を通したところ、所在でもっとも多い――といっても六、七人程度だが――のは”ハテノ村”だった。自分と同じ。
次点でハイラル城下町。いくつかの聞いたこともない地名に混じって、ぽつぽつと”なし”があるところに、絶妙な自分らしさが滲み出ている。
職業はもう少しバラエティに富んでいて、騎士、兵隊、農夫、馬丁、鍛冶屋、職工、料理人に旅人、変わりどころでは義賊がいる。いや、盗みを働いて生計を立てるなどとても褒められたことではないのだが、どんな経緯をたどったら自分がそんな職業を選ぶのだろう、というのには多少興味があった。
リンクは少し考えたあと、添えられたペンを手に取って、二十三、リンク、ハテノ村、旅人、と記入した。
馬鹿馬鹿しいにもほどがあるが、どうせ夢だか幻だかのことだ。
そして赤シャツの言うように、確かに、ちょっとだけ面白い。
赤シャツは興味津々というように、カウンター向こうから身を乗り出してくる。
「旅人か。いいなあ。俺、旅に出たいんだよね。この人が未来の俺の可能性ってことはないのかな」
近衛服は苦笑した。
「難しいな。同一の可能性同士は干渉することはできないだろう。世界が分岐するタイミングによっては、あるいは似ることはあるかもしれないが、基本的には我々は別の存在、別の可能性だ」
「可能性? 」
「あれだよ」
質問に答えるかわりに、近衛兵はリンクの背面に向かって視線を投げた。
追うように振りあおぐと、ホール上方の壁に、でかでかとした横断幕が掛けられているのが目に入った。
そこにはまるで子どもが書き殴ったかのような拙いハイラル文字――リンクはこれを見て、事態の首謀者たちが誰であるのかを悟った。片言の会話とへたくそな字をあやつる森の小さな精霊たちは、本当にいたずらが大好きだ――、こう書かれていた。
”いまもっとも大変な危機に瀕している可能性を、あらゆる可能性が励ます会”
リンクはたっぷり十秒、それを見つめた。
五回ほど文言を頭の中で復唱し、目を閉じて反芻し、うつむいて沈黙したあと、頭を抱え、髪をぐしゃぐしゃに掻き、唸り、天を仰いだのちに、元の姿勢に戻った。
「リアクションが身体に出るタイプなんだな。自分と違う系統を観察するのは面白い」
近衛服の失礼な感想は無視して、つまり、とリンクは言った。
「ここにいるのは”俺”は俺じゃなくて、……色んな世界……っていうことでいいのか……で、こうあったかもしれない俺、……つまり”俺”の”可能性”が、ここに集められてる、っていうことなのか」
「飲み込みが早くて助かる」
近衛兵は微笑んだ。
「おそらくは、君の言った通りだ。私たちは、あらゆる可能性によって分岐した無数の世界のそれぞれに存在している”リンク”だ。それらが超常的な力によって、それぞれの世界から切り離された時間、空間のもとで一堂に会しているのだろう。世界が個々に独立した存在だと仮定すれば、こうして会話をしたり接触することに矛盾はない。納得するかしないかは別として、一応、辻褄は合う」
リンクは感心した。
言っている内容そのものではなく、あまりにも堂に入った賢そうな言い方に、だ。
「もしかして、学者になった可能性?」
「まさか」
近衛服は肩を竦めた。
「いくら可能性には限りはないからといって、根っこは私だろう? 頭の出来にそこまでの幅はないよ。妻がそちらの専門家で、よく話に付き合っているだけだ」
なかなか厳しいことを言ってくれるが、それはおおよそ真実のように思われた。自分の頭の程度は、自分が一番よく知っている。
それに、と近衛服は詰まった襟元の布を引っ張った。肩から胸元へと渡された何本もの金モールが、重たそうに揺れる。
「近衛兵は兼業禁止だ」
リンクの知っているハイラル王国とさほど違いがないのであれば、これは階級を表しているはずだから、この”可能性”は、ずいぶんと出世したらしい。
いい格好だな、とリンクは素直に思った。品があるし、よく似合っている。
自分の住む世界のハイラル王国は百年以上前に滅びてしまったが、あちらの世界ではまだまだ健在なのだろう。制服の放つ艶やかな絹の質感は、少し、ほんの少しだけれども、目にまぶしく映った。
「俺からしたら、これで分かるそっちもすごいと思うけどなぁ。何回説明してもらっても、やっぱり意味不明だもん」
カウンターにひじを載せて頬杖をついた赤シャツは、いかにも不満げに口をとがらせた。難しい話は嫌だ、つまらない、という態度を隠しもしない。
「ていうかさ、この俺も違うっぽいね」
「何が」
「私もそう思う」
「だから、何が」
「”いまもっとも大変な危機に瀕している可能性”」
赤シャツと近衛兵は、ほぼ同時に言った。声の高さは違っても音質が同じなので、綺麗に調和している。
「ここに来てから結構経ってるんだけどさ、まだそれっぽい俺が来てないんだよね。”大変な危機”っていうくらいだから、ぱっと見てヤバい!って感じのはずでしょ? でもみんな、割とのんびりしてるんだよなあ」
リンクはあらためてホールを見渡した。
言われてみれば、どの自分も各々なりに警戒心は持っているようだが、割合いに落ち着いているように見える。ことさら焦ったり、何かを訴えようとしている様子はなかった。元々、あまり他人を頼ろうとしない性分だというのもあるのだろうが――自分のことだからよく分かる――、危機というからには、もう少し余裕がない雰囲気を漂わせていてもよさそうなものだ。
「いちおう聞くけどさ、いま危機に瀕してたりする?」
「いや、特に」
リンクは頭をひねった。
日々の生活で困っていることはないし、ありがたいことに怪我も病気もなく、身体はぴんぴんしている。家人との関係はいたって良好だ。
昨日だって、ハテノ村の自宅でおだやかな時間を満喫していたのだ。
旅に生きるのは性に合っていて、何より楽しいが、そこでは味わえない喜びもある。暖炉でじっくりと煮込んだシチュー。焼きたてのパン。たっぷりと湯を張った浴槽。ふかふかのベッド、太陽の匂いのする清潔なシーツ。天候や獣の気配を気にすることなく、ゆるゆると過ぎていく夜の時間、などなど。
「困ったな」
近衛兵が言った。
「君が来るまでにも色々と試してはみたんだが、やはり目的が達成されない限りは、ここから出られないようでね。期待半分、不安半分で当該の自分を待っているというわけだ」
「不安?」
「その”危機”というのが、私たちで対処できる範囲のことだ、という保証がない」
確かに、とリンクは思った。
もしかしたら、自分たちではとても手に負えないような状況を抱えた自分が来るかもしれないのだ。
「”危機”、ねえ……」
リンクはカウンターに背をもたれかけながらつぶやいた。
百年の眠りで失った記憶はろくに戻ってはいないが、それでも、いままでの自分の人生の中で、どんな時に”危機”を感じたのかを思い出す。
単純に考えれば、強い魔物に遭遇したとか、崖で足を踏み外したとか、雪山で遭難しかけたとか、その手の状況が当てはまるのだろう。
ただ旅をしていれば、大なり小なりそういったことには遭遇する。
確かに”危ない”場面だが、そのいちいちを、ことさら”危機”だと騒ぐようなことはしない。”危機”になりえるとしたら、それは別の要件が付随した場合かもしれない。
例えば――自分ではなくて、彼女が、だったら。
「あっ」
リンクは思わず声をあげた。もしも自分が、心の底からの”危機”を感じるのだとしたら。
「え、なになに? 」
「どうした」
身を乗り出してくる二人に説明しようとリンクが口を開いたそのとき、ばん、と背後で大きな音がした。
リンクは思わず振り返り、そこには――もちろん、自分がいた。
「……なんだ、これ」
さきほどの自分とまったく同じセリフを吐いて、それは茫然と立ちすくんでいる。
よほどの勢いで扉を開けたらしい。フード付きのマントの裾が、まだゆらゆらと揺れている。
しかし、より注目すべきはそこではなかった。
右手だ。
その様子は明らかに、自分とも、この場にいるすべての自分たちとも異なっていた。
ひじから下が、黒とも緑とも言えない色に染まっている。何かを装着しているのでも、色を付けているのでもない。皮膚そのもの、もしかしたらその下にある血肉そのものも変質しているかもしれない。
形もまた異常だった。本来なら指先に相当するであろう部分が、まるでかぎ爪のように尖っていた。
よく言えば獣、悪く言えば魔物。
金属とも石とも見える奇妙な帯でぐるぐると縛られた腕は、それ自体が異形の生き物のようであり、かつまた、それらに抗するための呪具のようでもあった。
リンクはそれらを観察し終えたあと、ゆっくりと背後に向き直った。
赤シャツと近衛兵、三人の視線が合わさる。
全員が頷いた。
――間違いない。こいつだ。
入ってきたばかりのマント――便宜上そう呼ぶことにする――は、忙しなく周囲を見渡して、壁のところどころを触っている。
気持ちはよく分かるが、もちろん、例のごとく扉は消失してしまっている。
「こっちだ、こっち」
リンクが呼ぶと、マントは振り向いた。
二十歳前後にはなっているだろうか、そこそこ大人じみた面構えをしている。
マントはつかつかとこちらに歩み寄ってきて、きっぱりとした口調で言った。
「戻りたい。帰してくれ」
「そうしたいのはやまやまなんだが、ちょっと込み入った事情があるんだ。立ち話もなんだから、まあ座ってくれ」
リンクは空いたスツールを示したが、マントはすげなく断った。
「このままでいい。急いでいる」
「まあまあ。そう言わずに」
一段と明るい声を出して、赤シャツが割って入ってきた。
「腹減ってない? 何か食う? 」
「いや、本当にいい。……放っておいてくれ」
「よほどの急用のようだが」
近衛兵の言葉に頷いたものの、マントは用心深げに目を凝らしてこちらを見るだけだ。少なくとも、和気あいあいと語り合おうという気はないようだった。
これはまた、随分と警戒心が強い自分がきたものだ。
リンクは驚くと同時に、ひとつの直観を得た。
基本的にはおおらかで鈍感な自分が、こんなにまで神経質になる原因は、おおよそあのことと相場が決まっている。あくまで自分の基準でしかないが、相手も自分なのだから、あながち外れもしないだろう。
「ゼルダに、何かあったんだな」
瞬間、さっとマントの顔色が変わった。当たりだ。
「知っているのか!」
どこからそんな声が、と思うほどの絶叫だった。
空気がびりびりと震えて、リンクはとっさに耳を塞いだ。
「どこにいるんだ! 無事なのか、怪我は、いったい何が、どうなってあんな、……いや、細かいことはいい。何でもいい、とにかく会わせてくれ!」
「落ち着け」
このまま喉が枯れるまで叫び続けるのではないかと思われたマントを制したのは近衛服だった。
「どれだけ取り乱したところで、ゼルダという人はここにはいないし、我々は何も知らない」
マントはきっと近衛服をねめつけたが、近衛服は動じなかった。眇めた目に威圧感すら漂わせ、真正面から視線を返している。
「頭に血が上っているときは、自分一人の身もあやうい。剣を持つものとして、その程度のことが分からないわけでもあるまい。……もっとも、今は正論を聞くのも辛いのだろうが」
「……」
しばらくそのまま、睨み合いが続いた。
近衛服が勝つな、とリンクは思った。近衛服の目は、人にものを命じることに慣れた人間のそれだった。伊達にごてごてとした飾りを付けているのではない。踏んできた場数が違う。
はたして、予想は当たった。
じりじりとした沈黙のあと、先に視線を切ったのはマントの方だった。勝ち目はないと踏んだのか、いかにもしぶしぶとではあるが、少し離れたスツールに腰をかけた。
「はい、お待ち」
すかさず赤シャツが差し出した皿の上には、サンドウィッチが山と盛られていた。いつの間に用意していたのか、軽く焼いたパンに、チーズと数種類の野菜、薄切りにしたハムらしきものまで挟まっている。
「とりあえず腹に入れておきなよ。あんまりもの食ってなさそうだし、それじゃテンションもおかしくなるって」
「だから、本当に……」
「人間、食べなきゃ始まらないよ。まあ、これはゼルダの受け売りなんだけど」
マントは驚いたように動きを止めて、何度も瞬きをした。
「……名前」
「うん?…… ああ、ゼルダね。俺の幼馴染。ちょっと口うるさくておせっかいやきだけど、すごく優しい子だよ。いつでも俺と一緒にいるんだ」
にこにこと屈託なく笑う赤シャツとサンドウィッチの皿を、マントはしばらく交互に見やっていた。
が、やがて小さな声で、いただきます、とつぶやいて手を合わせた。
淡々とサンドウィッチを口に運ぶ左手とは対照的に、異形の右手はいま、カウンターの上に行儀よく置かれていた。つくづく不気味な形状をしている。なまじ人であった時の姿を想像できるだけ、異様さが際立っている。
彼もまた長く旅をしているのか、身に着けているマントはくたくたで、よく見ると、自分のものに似たデザインをしていた。
だとすると、近衛服の話に沿うなら、かなり近いところで”分岐”した世界の可能性、なのかもしれない。
旅人。もしくはそれに類することを生業とする者。
それが事件なり事故なりに巻き込まれて、こんな具合になり、ゼルダと離れ離れになった、というところだろうか。
正直、
(こんな姿になってまで)
と、リンクは思う。
こんな姿になってまで、”自分”はゼルダを必死になって探し求めている。
しかし、こんな姿になってもなお、という切実な気持ちも、リンクには分かる気がした。
だって、ゼルダだ。
リンクだって、もしもゼルダがいなくなって、リンクがどこかおかしくなって、それでもどうにか体が動くのなら、そこが世界の果てでも、そのさらに向こうのどこかだったとしても、リンクはゼルダを探しに行くだろう。
それはどんな可能性の世界であっても、自分が自分であり、ゼルダという存在がそこにある限り、きっと変わらないように思えた。
「会えるよ」
と、リンクは言った。
「思っているようにはいかないかもしれないし、今までよりももっともっと、苦しい思いをするのかもしれない。でもきっと、お前はゼルダに会えるよ」
手を止めて、マントはリンクを見た。
「根拠は」
「ない」
リンクは首を振った。
「でも、俺の――俺の世界のゼルダは、ときどき言うよ。あなたを信じていることに、根拠なんてありませんって」
尖った黒い指先が、ぴくりと動いた。それを押さえつけるように、マントは自身の左手を重ねる。
華奢なようでいて、指はがっしりとして太い。ここまでの道のりが決して楽なものではなかったと主張しているかのようだった。
そしてそれはまごうことなく、自分と同じ、人の手の形をしている。
「……あのさ」
しばらくしておずおずと、赤シャツが小さく声をあげた。
「素朴な質問なんだけど。……どうして、皆が”ゼルダ”なの?」
「それは、我々がなぜ皆”リンク”なのかというのと同じ問題だな。ちなみに、我が国の聡明なる女王陛下のお名前もゼルダという」
するとそこに、
「すまないが」
と、また別の自分が割り込んできた。
顔つきはやや幼く、全身に鎧を着こんでいる。どんな可能性なのは知らないが――なにせ番号札を付けているわけではない――、目つきは真剣そのものだ。
「俺のご主君も、ゼルダ様という。もしかして、関係があるのだろうか」
こんなところに来てしまった自分よりもそちらのほうがよっぽど気がかりだというように、鎧は眉をひそめた。彼だけではない。気がつくと、リンクたちの近くには幾人もの自分たちが寄り集まっていた。
「俺のところもそうだけど」
「いや、自分も」
「うちだけじゃないのかよ」
途端に、ホールの中は騒がしくなった。
姿も雰囲気もてんでばらばらな自分たちが、ああだこうだと口々に、お互いの”ゼルダ”のことを言い合っている。
自分についてはこまごまと語る気はないが、こと”ゼルダ”に関しては別らしい。彼女が、あの子が、あいつが、お嬢様が。中にはいったいどんな関係性なんだと聞きたいものも混じっていたが、ともあれ、それぞれがそれぞれなりに、”ゼルダ”という人物に対して思うところがあるようだった。
「我々はよほど、”ゼルダ”という女性に縁があるらしい」
近衛兵は苦笑しながら、あっけに取られたように固まっているマントに向き直った。
「それこそ、根拠だの理論だのに関係なく。……私も、彼と同意見だ。大丈夫だ。いつか君は、ゼルダ嬢にまた会える」
俺も俺も、と赤シャツ。
「大丈夫だと思うよ。だって、俺とゼルダなんでしょ」
小難しい理屈がないだけに、それはまっすぐな確信に満ちていて、力強かった。
マントは右手をじっと見つめた。
親指から順に、ゆっくりと動かしていく。グロテスクな見た目とは裏腹に、それは精緻に、繊細に動いた。やがて力強く、ぐっと自身を握りしめる。
「……そうだな」
マントは立ち上がった。
いつの間にか、目の前の皿は空になっている。自分らしく、いい食べっぷりだった。
「ごちそうさま。美味かった。……ゼルダに会いに行ってくる」
と。
――テントトテン!
びっくりするほど空気にそぐわない、陽気で、ひときわ間の抜けた音が高らかにホールに響き渡った。
同時に、ポン、と壁の一部が小さく爆発する。もわもわと漂う白い煙の周りで、色とりどりの木の葉が舞っている。中から現れたのは、例の扉だった。それが彼のためのものであることは、誰の目にも明らかだった。
マントはいささかも躊躇くことなく、扉の前に立った。右手の黒く鋭いシルエットが、しっかりとノブを掴む。
「気を付けて」
「忙しくてもちゃんと飯は食いなよ」
「ゼルダ嬢によろしく」
またな、元気で、死ぬなよ。自分たちから掛けられる声援ともつかない掛け声に、マントは軽く左手を挙げて応えた。
もしかしたら、ちょっと笑っていたかもしれない。
そうリンクが思った時にはもう、マントは扉を開け放ち、その向こうに広がる暗闇へと消えていた。
ぱたんと音を立てて閉じられた扉を、ホールにいる全員が見つめている。扉は消えない。
「……これ、もしかして俺たちも使えるの?」
「そのようだ」
帰る、と一番に言い出したのは鎧だった。
「帰って、ゼルダ様をお護りしなくてはいけない。世話になった。またどこかで会えたらよろしく」
うん、とひとり納得したように頷いて、鎧は勢いよく扉を開けた。
その先が本当に自分の世界であるかどうかの保証はないというのに、日ごろから向こう見ずなところがあるのか、鎧はお構いなしだった。ずかずかと大股で敷居を跨ぎ越し、あっという間に扉が閉じられた。慌てて引き返してくるのではとひやひやしたが、しばらく待っても、鎧が帰ってくることはなかった。
「元の世界に無事に帰った、……ってことでいいのかな」
リンクの疑問に、おそらく、と近衛服は頷いた。
それが潮になった。
これにて一件落着だと判断したのか、自分たちが一人、また一人と扉をくぐって、元の世界へと帰っていく。
面白いことに、黙って出ていく者は一人もいなかった。誰もが皆、程度の差こそあるものの、周囲に礼なり挨拶なりをしてゆく。放っておいても問題ないだろうに、使っていた食器や椅子なども律義に片付けられていた。
よくゼルダは、あなたは真面目な人だから、とリンクに言う。
自分ではあまりその気がなかったが、いざこうして見てみると、なるほどこれは真面目な人間のすることだと、図らずも、ゼルダの人を見る目の確かさを実感する。
眠そうな目をこすりながら出ていった一番目を見送ると、ホールにはリンクを含めて、三人の自分が残った。
「これは私が預かろう」
カウンターに置かれたままだった出席簿を丁寧に折り畳み、近衛服はそれを腰のベルトに挟んだ。
「夢の証拠品として、このまま現実に持っていけたら面白いんだが。……まあ、無理だろうな」
「やっぱり、忘れちゃうのかなあ」
食器を仕舞い終えた赤シャツがカウンターから出てくる。
と、何かを思いついたらしい。
つまらなそうにとがらせていた口を、にいっ、といたずらっぽく曲げる。
「じゃあさ。せっかくだから聞きたいな。そっちのゼルダは、可愛い? 」
リンクは近衛服と顔を見合わせた。何ともまた、答えにくい質問をしてくる。
「いいじゃん。どうせ忘れちゃうんだし」
(それはそうか)
と、リンクは思った。何せ相手は自分自身だ。照れたり誤魔化したりする必要もないし、しょせんは夢の中なのだ。
リンクは素直に答えた。
「可愛いよ」
同じことを考えたのだろうか、ややあって、近衛服も柔らかな声で答える。
「可愛い人だよ。ひどく恥じらうので、あまり言わせてはくれないが」
そっか、と赤シャツは笑った。
「やっぱりそこも同じなんだね。安心した。……俺さ、ゼルダと約束してるんだ。いつか旅に出て、一緒に山向こうの平原を見に行こうって。とりあえず、めいっぱい働いて、こういうマントを買うところからはじめる」
「そうか。頑張れ」
リンクの言葉に、赤シャツはニッと白い歯を見せて応えた。
自分のこういう表情は見慣れないが、悪くない、とリンクは思った。今度ゼルダに見せてみようか。きっと驚くだろう。
じゃあね、バイバイ。大きく手を振りながら、赤シャツは扉を開けてその向こうへと消えていった。
「さて。我々も行こうか」
手櫛で髪を軽く整えたあと、近衛兵は制帽を被って立ち上がった。
「私が最後に残ろうか」
「いや、俺が残るよ。今さらだけど、”王様”って忙しいんだろ?」
近衛服は目を丸くした。まじまじとリンクを見やる。
「気がついていたのか」
「まあ、うすうすと」
賢い専門家の妻がいて、ものすごい出世をしていて、人に命令をする立場で、交渉ごとにも慣れている。
ハイラルの現女王陛下は妻と同じように賢くて、彼はその王座を護っている。
それらの情報に、こうだったらいいな、という希望を加味すると、おのずと結論は見えていた。
「細かいことを言うと、”王様”ではなく、”王配殿下”だ。陛下の護衛も兼ねているから、忙しいのは確かだよ。だが、やりがいのある仕事だ」
近衛服は淡々としていたが、その横顔は誇らしげだった。
「近衛兵は兼業禁止じゃないのか」
「婚姻関係を兼業とは言わないだろう。……そっちこそ、そのことは最後まで言わなかったな」
「え? 」
「ゼルダ嬢と結婚して何年になる」
今度はリンクが驚く番だった。
「どうして分かった」
「妻帯者としての勘、かな」
近衛服はにやりと笑った。
「付け加えるなら、”ゼルダ”の話をしている時の顔だ。他人にしては距離が近いが、親兄弟にしてはぞんざいなところがない。恋人というには落ち着きがある。そんなところか」
リンクはあきれた。
「よく見ている」
「護衛はそれが仕事だ」
なるほど、要人警護には観察力が求められる。他人を注意深く観察する癖がついていてもおかしくはない。リンクは観念した。
「式を挙げたのは三年前だよ。元気に暮らしてる。厄災後のハイラルをまとめる盟主になるか、フィールドワークに生きる学者になるか、まだ決めかねているみたいだ」
それはいい、と近衛服は微笑んだ。
「こちらのゼルダは、最近仕事が立て込んでいて塞ぎがちだ。近々また、野外研究に連れ出そう」
扉の前で、リンクたちはお互いに立ち止まった。
「じゃあ、また? 」
「そうだな、また。奥方によろしく」
「そっちも」
近衛服は頷いて、これ以上ないくらいに整った敬礼をした。静かに扉は開かれて、また静かに閉じられた。
ホールには、リンクだけが残された。
(ふりだしに戻る、だな)
来た時と同じように、目の前には扉だけがある。
何の変哲もない扉。手にしたノブの感触を確かめながら、おかしな夢だったな、とリンクはあらためて思った。
当初はどうなることかと思ったが、結末は悪くないし、なにより面白かった。知り合い――といっても自分自身だが――も増えた。
名残惜しさがないわけではないが、といって、ここで突っ立っていても仕方がない。
リンクは扉を開けた。
暗闇が広がっているとばかり思っていたが、そこは真っ白な光で満たされていた。
ああ、そうだ。
リンクは思い出す。
昼寝をしていたのだった。
朝から素晴らしい陽気で、洗濯物を干したあと、庭の木の下に寝転がった。しばらくすると、ゼルダが近寄ってきた。本当はそこで起きてもよかったが、髪を梳いてくれる指があんまり気持ちが良くて、リンクは寝たふりを決め込んだ。やがて本当に眠くなってきて、そして、そして。
(ゼルダに会いたい)
と、リンクは思った。
無限に広がる可能性の世界の中で、ただ一人の自分だけが出会うことのできた、同じようにただ一人のゼルダが、この光の向こうにいる。
それがどんなに素晴らしいことなのか、出来るなら、ゼルダに語りたい――もちろん、覚えていられればの話だが。
足元がふわふわとしておぼつかなくなる。
意識が浮き上がっていく。
どこからか聞こえてくる細い声。それは自分の名を呼ぶ彼女の声だ。
いつでも自分を、あるべき世界へと導いてくれる声。
(早く、ゼルダに会いたい)
ここを通っていったすべての自分が願ったであろうその言葉を胸に、リンクはそっと目を閉じた。
〈了〉