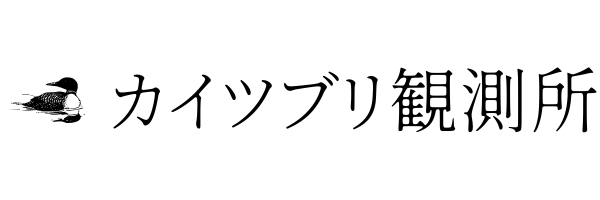まわる、まわる
踊る気はなかった。
にぎやかなさまを見ているだけで十分に楽しかったし、明日はこれといった予定もないからと口にしたワインのせいで、少々酔ってもいた。
だから私がこうして踊り場に立っているのは、ひとえに、リンクの誘い方が上手だったからだ。
「行こう」
そう言って私の手を取った彼の動きは、あまりにも自然だった。
あんなに真っすぐに見つめられながら誘われたら、断り切れる女性なんて、きっといない。
リンクは普段強く出ることのない分、ここぞというときに、そういう顔をする。
ただ、半分くらいは恋人としての欲目かもしれないので、それをしてずるい人だという指摘はあたらないのだろう。
「なにか勘違いしているのかもしれませんが」
左手で私の手を握り、右手で私の腰を軽く抱いたリンクに、私は言った。
「私、あまりダンスは得意ではありませんよ」
お城の姫君だったからといって、おとぎ話のようになんでも優雅にこなせるわけではない。
人であるからには当然得手不得手があるわけで、私の場合、ダンスは後者により近いところにある。
そうなんだ、とリンクは言った。
「大丈夫だよ。ゼルダに合わせるし」
「足を踏むかもしれません」
「踏まれる前に避けるから、心配しないで」
リンクの身体能力を考えれば、それは真実なのだろう。もちろん発言の主旨はそこではなかったのだが、うまくリンクには伝わらなかったらしい。
私はため息をついた。どうやらリンクは、踊るという選択肢をあきらめる気はなさそうだ。
楽隊は陽気な曲を奏で続けている。二本の弦楽器、横笛、地面にじかに置かれた太鼓といくつかの小ぶりな打楽器。それにリト族の吟遊詩人が使っていた、独特の蛇腹の鍵盤楽器の組み合わせ。体系化された音楽ではないけれど、速度の速い四拍子は気軽で愉快で、聴くだけで心がはずむ。
それに合わせて、旅人たちが思い思いに踊る。
たいていは二人組で、でたらめな――正規のダンス作法からすれば、だ。もっともそんなものは百年前に国が滅びて以来、このハイラルから姿を消した――ステップを踏み、ふらふらと不安定にターンする。
踏み外しては互いの足を踏み、ときには回りきれずに尻もちをつく。が、笑いながら手を取り合って、また踊り出す。
昼には馬宿に接する大池を一望できるテラスは、いまやれっきとしたダンスホールになっていた。
目の前には、期待に満ちた目で私を見つめるリンクがいる。右半身がぴったりとくっついているから、距離が近い。
その視線の強さと、久しぶりのダンスへの緊張とで、私はひどく、どきどきした。
「……では」
息を飲み、震えながら、右足を前に出す。
右、左、右、左。交互に足を出す基本のステップを二回。三回目は軽く跳ね、身体をねじって半回転。向きを変えて、もう一度最初から。ステップ、ステップ、軽く跳ねて、半回転。ステップ、ステップ。
ああは言ってくれたが、やはりリンクの足を踏むのは嫌だし、怖かった。
出来る限り失敗のないよう、地味だがそつのない動きを繰り返す。
(変化がありません、姫様。もう少し思い切った動きを。……回転が歪んでいます。しっかりとパートナーをホールドして)
思い出の向こうから、私でない人の声がする。
あのころの私には、様々な教師が付いていた。
各種の学問、礼儀作法、家政技術に芸術全般。それぞれの分野の専門家が私を指導した。
今思えば、父はその人選によほど心を砕いてくれたのだろう。
私が王位継承者であるからといって、おもねったり手心を加えるような下劣な品性をもった人は、一人としていなかった。
ダンスの教師は、その特徴が顕著な人だった。
細身の中年の女性で、つねに硬い表情をしていた。身体のすみずみまで緊張感が行き届いていて、ぴんと張った背筋が、実際よりもずっと上背があるように見せていた。
その表情と同じように厳しく、また、正直な気質の人だった。
出来ないところは容赦なくずばりと指摘してくるかわりに、それができるようになると、惜しみない称賛を贈ってくれた。そういう時の彼女の拍手は、素晴らしく澄んだ音がした。
ある日、こんなことを言われた。
「姫様は、断じて下手なのではありません。基本はすべて出来ています。音曲への理解や、場をながめる広い視野もお持ちです。しかし、優雅ではない。特にターン、回転運動に問題があります」
私はうつむいて、ぐっと唇を噛んだ。
向きを変える程度ならまだ堪えられたが、くるりと一回転、ともなると、私の身体は必ずどこかでバランスを崩した。
何度も訓練するうちに、おいそれとは気がつかれないだろうというくらいには誤魔化せるようになったが、根本的な解決になっていないことは、私が一番よく知っていた。
教師は言った。
「姫様。回転をともなうダンスに重要なものは、なんだと思いますか」
しばらく考えて、私は答えた。
「正しい姿勢と、柔軟性です」
「いいえ」
教師はゆっくりと首を振った。
「相手への信頼です」
「信頼? 」
意外だった。
そんな観念的なことを持ち出すような人だと思っていなかったので、私はとても驚いた。
教師は頷く。
「精神論ではございません。実践的なお話しです。いいですか。回転で重要なのは、軸です。パートナーを心から信頼して身体を預け、ふたりの身体でひとつの軸を共有する。それが優雅で力強い回転には不可欠なのです。それだけではありません。静止した時の美しいシルエット。安定し整ったステップ。信頼こそが、すべての要素をより良いものへと変えてゆきます」
力を込めて、教師は言った。
「いつか。——いつか、心から信頼できるパートナーと出会ったあかつきには、おのずと分かります」
私は小さく、はい、と答えた。
当時の私は王家の姫としての責務を果たせず、無才だ役立たずだと陰口を叩かれ、軽い人間不信に陥っていた。
誰かを心から信じてすべてを委ねるなんて、ダンスを踊れるようになるよりも、はるかに難しいことのように思われた。
「さあ、正しいポジションをもう一度確認しましょう。互いの右半身を密着させて。そこが重心になります。しっかりと意識をしながら、腰に添えられた手を感じてのびやかに身体をひらく。顔をしっかりと上げて。……明日、そのパートナーが現れるともかぎりません。予習は入念に」
それがお堅い彼女の精いっぱいの冗談だということは、すぐに分かった。
あまり気が利いたものとは思えなかったし、顔だって、いつもと変わらない愛想ひとつもないものだった。
しかしそれは、ぎこちないながらも不肖の弟子へのいたわりと慈しみに満ちていて、私は泣きそうになるのをどうにかこらえた。
――そんなことが、かつてあった。
「ゼルダ」
はっとして、私は現実にもどった。
気がつけば音楽は止んでいた。あちこちからまばらな拍手が起き、細い口笛が鳴っている。
私たちは踊りの輪の隅っこにいた。リンクは私を抱き寄せたまま、なにかを思案するように首を傾げている。
寄った眉根に、心がざわざわと騒ぎだす。自分では気がつかないうちに、どこかで失敗をしたのだろうか。
「あの、私……」
「難しいな」
「え?」
リンクは独り言のようにつぶやいた。
「回るところ。剣を振りまわす要領でいけるかなと思ったんだけど、やってみたら全然違った。もっと上手くやれる気がするんだけど、どこがいけないんだろう。やっぱり、重心の置き方なのかな」
「重心……」
うん、とリンクは頷く。
「ゼルダはどうしたらいいと思う? 」
楽団員のほがらかな声が聞こえる。さあ、次で最後です。最後にふさわしい、とっておきの一曲をご披露しましょう。みなみなさまもどうぞ、心置きなく踊って、回って、お楽しみください。夜風に乗って、歓声と拍手が流れていく。
私はリンクに身体を寄せた。
服の向こうにある肌の熱さと息遣いまでもが聞こえそうな距離。うっすらとした汗の匂い。
こんなに密着しても、少しも不快にならない。それどころか、安心すら覚える。
この人なら、リンクなら、大丈夫。
「お願いがあります」
私は身体の右半分を、リンクのそこに密着させた。背筋を伸ばし、顎を引く。
「私を、離さないでくださいね」
細かい説明はしなかった。
繋いだままの手を、強く握りこむ。ただそれだけで、伝わるような気がした。
「もちろん」
と、リンクが耳元で囁いた。
「頼まれたって離さない」
弦と笛と太鼓とが、いっせいに鳴った。
私は大きく右足を踏み出す。
四拍子、目がくらむような速さ、弾けるようなリズム。音楽は私たちに誘いかけてくる。回って、跳ねて、回って、もっと。
ぴったりと繋ぎ合わさった私たちの右半身。
その揺るがない軸を中心に、身体を遠く外へと投げ出して、私は回る。
リンクの手は決して離れない。むしろ離れようとすればするほど、彼は私を力強く抱き寄せる。大きく外へと踏み出す私の足とそれを引き留めるリンクの腕。私たちが描く軌道は、優雅で大きな円となる。
高速で景色が流れていく。
他の旅人たちの顔も、楽団も、さかんに燃えるたいまつの灯も、騒がしい夜の気配も。
こんな世界があったなんて。
驚く私のすぐ目の前に、楽しそうに笑うリンクの顔がある。音楽は鳴りやまない。私たちは回り続ける。息はすっかり切れていて、胸が破裂しそうなほどにどきどきとしているのに、足はより軽やかに、より自由に床板の上を滑っていく。
教師の言葉は本当だった。信頼は、あらゆるものを変えていく。
すべてが終わったとき、私たちはフロアの真ん中にいた。
「ブラボー! 」
万雷の拍手が、私たちを包むように響いた。はやし立てるような指笛に合わせて、楽団員たちが思い思いに楽器を鳴らす。誰もが熱に浮かされたように笑っている。羨ましいぞ、なんて揶揄する声まで混じっている。
思わず周囲を見回した私を、リンクは両腕でぎゅっと抱きしめた。
人前ですとか、恥ずかしいとか、そんな理由をつけて拒むだけの余裕は、もうなかった。今になってワインが効いてきたのか、身体がふらふらとしておぼつかない。もうどうにもならなくなって、私はリンクの胸に顔を押し付けた。
拍手が一層大きくなった。
夜空に響き渡るそれは、素晴らしく澄んだ音がした。
〈了〉