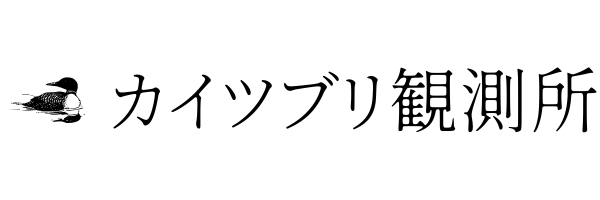少し遅くなりましたが、10月の月報です。
イベント参加情報に一件追加しました。
・11/2(日)SaGa Allstars10(サガオル10)@東京文具共和会館3階
「サークル+カイツブリ」で、前回と同じくサトーさんと合同で、ヴィクトール×最終皇帝(女)で参加します。
カップリングの略称すらどうしていいのか分からない手探り感ですが、本人はいたって大真面目に書いてます。
いまはひたすら書き進めているところですが、終わったらまた雑記等で語りたいです。兄さんも終帝子ちゃん(仮名)も幸せになってほしい~!
・11/16(日)Memoryofregend 7@東京ビッグサイト
新刊(再録本二種)が確定しました。完売分の既刊+書き下ろし+一部Web再録(R18のみ)、という構成です。
以前書いたものは思ったほど「きっつい!」とはならなかったのですが、逆にいうと伸びしろがないというか、新鮮味に欠けているというか……。いつもながらのご家庭の味つけといった感じです。
何より、今リンゼルについて何か書こうとすると封印戦記のことが頭をちらついてしまって集中できない。なんだあのゴーレムは!(第一声)
あと姫様の肩甲骨や二の腕が無防備に晒されていることにも気が休まりません。早く!早く上掛けを!と私の中の近衛がうるさい。姫様の骨格は私が護る。
最近のこと。
原稿中は読書をやらないほうがいいと最近学んだので(読むのが楽しすぎて完全な逃避になってしまう)、映画を見たりしています。
今月見たもののうち、『ファーザー(2020/アメリカ・カナダ・フランス)』が印象的でした。
認知症になった高齢男性の見る世界と、家族の姿を描いています。主演のアンソニー・ホプキンスがこれでアカデミー賞を取ったので、ご存じの方も多いのかもしれません。
私は寡聞ながら初めてだったのですが、観たあとに思ったのは、「フィクションは偉大だな」ということでした。
ケアの文学や映画、なかんずく物語はなかなか世に出でこないという印象があるのですが、おそらくその原因の一つに、「あまりに生々しくて描けない」という側面があると思っています。
ケアの実際は、世の中で喧伝されているほどドラマティックではないし、感動的でもない。
誰が悪いわけでもない、けれどどんどんうまくいかなくなる生活。じりじりと社会からはみ出していく感覚。削られていく体力と気力。
そういった実情を訴えるために、特にケアや医療においてはノンフィクション/ドキュメンタリーという手法が多く取られるわけですが、ではノンフィクションならリアルに表現できるか、というと、意外にそうでもない。
被写体も人間なら撮る側もやはり人間ゆえ、生々しい負の感情や無力感を前にすると、つい覆い隠したくなる。定型文の感情とか、いい感じの言葉とか、それらしい意味合いを貼り付けて描いてしまう。
でも、それはしょうがない気がするんです。リアルにそこで苦しんでいる人に、ついつい助け舟を出してしまいたくなるのが人情だし。そこで現実突き付けて突き放すのがいいなんて、口が裂けても言えない。
だからこそ、「フィクションであること」が活きてくる。
フィクションだからこそ、カメラ=視線は追い続けられる。
老い、記憶が定まらない不安と戸惑い。その裏返しの怒り。ままならない身体と自尊心。家族への思いと関係はつねに移り変わり、社会は合理性という名の冷たい目線を向けてくる。
ラストシーンは本当に苦しかったです。家族も本人も本当に苦しい。
でもそれを誤魔化さず、徹底的に描ききっている。
この描ききれる、というところに、フィクションは意味があるのだと思いました。
ドキュメンタリーだったら直視できない。きっと認知症辛い、こんなふうになりたくないっていう恐怖だけが残る。
でもアンソニー・ホプキンスの希代の名演だから、作りものだから、嘘だからこそ、最後まで見ていられる。
そして辛い、苦しい、悲しいという生の感情とは少し距離を置いて、あらためて「ケア」って何だろうという問いを残せる。
そんな気持ちになりました。
あと普通に家族と『ヒックとドラゴン』の実写版を映画館で観たのですが、とっても楽しかったです。
ドラゴンたちが可愛すぎた。狩るのもいいけどやっぱり乗りたいよな!(妄想の方向性がバトルに向かわないタイプ)
今風だな~と思ったのは、仲間のドラゴンオタク少年の解説が「これはファイアータイプ」「スピード10,重量16」みたいな言い方だったことです。スペック羅列的~!オタク!と直感的に分かる台詞回しが面白かった。
今月はこんな感じで。それではまた!