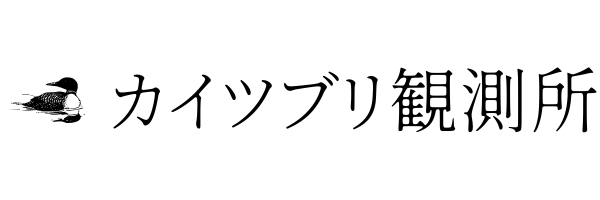「まあ」
ゼルダが感嘆の声をあげる。
見上げた先に、星空が広がっていた。
深い群青色の空の上に、小さな星がいくつも散らばっている。
月はなく、うっすらとした雲がところどころに掛かっていた。
地平との境目がほの白く発光して、遠い山々の形を浮かび上がらせる。デスマウンテンの噴火口から流れる溶岩が、脈打つように朱色に輝いていた。
どんな仕組みで天井の布を払ったのか、とか、晴れなかったらどうするつもりだったのか、とかいった疑問は、この際、些末なことだった。
リンクはゼルダと同色のマントの襟をかき寄せながら、空を仰ぐ。
用意してくれた席はぴったりと横並びで、隣との距離はほとんどなかった。
ロベリーは脚立に乗り、望遠鏡の最後尾に、何やら細長い部品を取り付けている。
夫人が手元を照らすためにランプをかざすと、サンキューである、オーキニ、と短く言葉を交わす。お揃いの木綿の上着は袖たっぷりとしていて、とても温かそうだった。
やがて大きな望遠鏡に、小さな望遠鏡がくっ付いた。
細身で、やはり黒い。金属製の筒口がリンクの肩くらいの高さにある。
そこを覗いて上空を観測するのだということくらいは、リンクにも分かった。
バッチグーである、と夫人と同じ口調で言ったあと、ロベリーは脚立から飛び降りた。
彼がふっと息を吹きかけてランプを消すとあたりはぐっと暗くなり、その分、夜空が近くなった。
「先日、ベリーインタレスティングな発見がありました。姫にもぜひ、お伝えしようと思い立った次第です」
「私に?」
「もちろんリンクにも」
思い出したように付け加えられて、リンクは苦笑した。忘れられてはいなかったらしい。
「論より証拠だ。まずは観測してみよう。ユー、リンク」
「俺ですか」
急な指名に、リンクは驚いた。そこは話の流れからして、ゼルダなのではないだろうか。
しかしロベリーは気にするふうもなく、イエス、と手招きをしてくる。それ以上、特に説明をする気はないらしい。
リンクは席を立ち、望遠鏡の側に寄る。
あの星だ、とロベリーが指差すのは、どこにでもあるような白い星だった。
天の高くも低くもない中途半端な場所で、ぽつりと浮かんでいる。
目を引くような輝きはなく、何かの目印となるような特徴もなかった。
訝しみながら、リンクは少し腰をかがめ、右目を筒口に押し当てる。
視界が一瞬暗くなったあと、すぐに光が見えてくる。
映し出されるのはぼんやりとした一つの――。
(あれ?)
リンクはいったん目を離し、大望遠鏡の先を見上げた。
まっすぐに伸びた太い首の先にあるのは、うすぼんやりとした夜の色と、やはり地味な色をした星が一つきりだ。
ふたたび、筒を覗く。
そこには数えきれないほどの光があった。
星は生まれたての真珠のようにくっきりと白く丸く。
周囲の薄闇はちりばめた砂金の海のように。
そこには確かに、肉眼では捉えることのできなかった光たちが、しっかりと息づいていた。
(凄い)
別世界かと思うほどの違いに圧倒されて、リンクは筒の中と外とを、何度も行き来した。
「どうかね」勝ち誇ったかのようなロベリーの問いかけにも、
「……増えてます」
と答えるしかなかった。
私にもぜひ、と近寄ってきたゼルダに、リンクは場所を譲った。
ゼルダはしばらく観察したあと、ほう、とため息をもらした。
「素晴らしいですね。肉眼ではとらえられない光も、望遠鏡を用いれば、こんなにもはっきりと観測できる。それに城の研究室で見たものよりも、いくぶん数が多いように思えます」
「鏡のサイズでしょう。シュウコウリョクはユウコウケイに比例します。つまり、大きさこそすべて。シンプルな理由ですな。――どうぞ、お座りください」
促されるまま、リンクとゼルダは席に戻った。
「ガーディアン研究には、三つの分野があります」
ロベリーの言葉には、老人らしい小柄な体を忘れさせるくらいの力強さがあった。
「動力となる古代エネルギー、ボディに使用されるレアーな素材、そして、ウェポンである光学兵器。天体観測は光学研究の実践そのもの。ミーの専門領域と言っても過言ではないのであります」
いつの間にか、夫人が近くに座っていた。
大望遠鏡の下をうろうろと歩きまわりながら熱弁するロベリーを、微笑みながら見つめている。
「古来より、人は星と親しんできました。そしてまた、天体観測はサイエンスとブラザー、いえ、ツインズといってよい関係性にあります。ウィたちシーカー族も、天体の運行を知るために、その優れたテクノロジーを磨いたという説もあるほどです。バット、実のところ、天体にはいまだに謎が多い。その最たるものは、距離です」
「距離?」
ゼルダの問いに、ロベリーは頷く。
「我々が見ているあれら恒星は、”ここ”からどの程度の距離にあるのか。シンプルかつ、ディフィカルトな問題です。――さて、ミーはガーディアン研究の一環として、長年、この望遠鏡を改良しつつ観測を続けてきました」
皺だらけの手が巨大な筒を叩くと、ゴンゴン、と低い音がした。
接合部に絡みつくように描かれた古代文様が、黒い胴体から浮かび上がっている。
「そして近年、思い付いたのです。ミーとワイフの研究成果、そしてこの望遠鏡があれば、星々との距離を計測できるのではないかと。ミーたちはあの白色の恒星をサンプルとして、さまざまな実験検証をおこないました。光の性質を波のようなものと考える従来の定説に縛られることなく、ミー独自の仮説であるケイシジョウテキアプローチデアルトコロノリュウシテキセイシツ……」
「ドクトル、戻シテ戻シテ」
すかさずすべり込んできた夫人の苦笑は、絶妙なタイミングで夫の暴走を止めた。
ロベリーはしばらく口を開けてぽかんとしていたが、やがて、しまった、と言うように額をはたいた。
「オウ、ソーリー。脇道に逸れましたな。……結論から申し上げましょう」
おほん、とあらたまった咳をして、ロベリーは言葉を切った。
まっすぐにのばした人差し指で天を指し示し、きっぱりと告げる。
「あの恒星は、ここから約千百兆キロメートル先に存在します。体感的に分かりやすい時間に換算しますと、光の速さで百二十年かかって到達する距離、となります。……つまり我々は今、百二十年前に発せられた光が”ここ”にたどり着いた、その瞬間を見ているのです」
百二十年。
「百、二十年……」
リンクが息を飲んだのと、ゼルダがつぶやいたのは同時だった。思わず顔を見合わせる。
リンクが生まれた年だ。そして、ゼルダが生まれた年でもある。
リンクは騎士の家の子として、ゼルダは世継ぎの姫として。
大厄災に見舞われる前の、まだ何もかもがあったころ。
「……それは、どのくらい確かな数字なのでしょう」
「グッド!」
パチン、とロベリーが指が鳴らす。
「姫。正確性を確認する、サイエンティストとしてまことにグッドな視点です。お答えいたします。可能な限り検算をおこなっていますので、現時点では十分に信頼できる数値です。が、観測精度の向上、再現性、検証手段の確立など、プロブレムは山積みです。つまりプロジェクトはまだまだ途上、いや、第一歩を踏み出したにすぎません。ハウエヴァ、この研究は必ずや、ハイラル復興の一助になると、ミーは確信しております。今後は光線の色、つまり星のカラーと温度との関連性にも着目し、ゆくゆくはエネルギー伝達機器のディヴィロップメントを――」
ロベリーの舌は、ますます熱を帯びていく。
しかし相反するように、周囲の温度は下がっていく一方だった。
リンクは小さく身を震わせた。
屋根はないし、破れた外壁からは風が吹き込んでくる。ほとんど野外といっていい環境なのだから、当然といえば当然だった。
やはり、ここは季節が進んでいるらしい。この旅の中で迎えたどの夜よりも、冷え冷えとした空気を感じた。
じわじわとブーツの底からしみ込んでくるような冷たさに、ぐっと歯をかみ締める。
するとまた、あの大音量が床下から轟いた。
『時間デス。ワレ、時間デス』
「うわっ」
「きゃ」
「ワット?」
「アラ、もうそんな時間」
突然のことに目を丸くするリンクたちを尻目に、夫人は澄ました顔で立ち上がる。
「ダイジョーブ、すぐに止まります。タイマー、ホントに便利」
その言葉の通り、シーカーレンジが叫んだのはその一度きりだった。夫人は笑った。
「コノママだと、徹夜コースデスカラネ。そろそろオ開きにしましショー」
オウ、とロベリーが天を仰ぐ。
「バット、ワイフよ、本題はここからであって……ッ」
くしゅん。
短いが派手な音を立てて、ロベリーの小さな鼻からくしゃみが出た。続けて二回。
ぐずぐずと袖で鼻下をぬぐう夫の背をさすりながら、夫人は笑う。
「ネ。お身体にさわりますカラ」
そこから夫人は、鼻をすすりつつ、なおも名残惜しいという体で渋るロベリーを、にこやかに、かつ毅然とした態度で、ねばり強く説得した。
三十年以上連れ添っているだけあって、そのあたりの塩梅は見事なものだった。
「ジェリンさんの仰る通りです。身体を大事にしてください、ロベリー」
結局ゼルダのその一声で、ロベリーは折れた。
明日また改めて、と何度も念を押しながら、彼は就寝の挨拶をして一階へと下りていった。
片付けのコトは気にしないでネ、ドウゾごゆっくり。ひらひらと手を振りながらそんなことを言い残し、夫人もまたを後を追った。
階の上下を仕切る板が降ろされてしばらくは、床板の向こうから、種々の生活音が聞こえてきた。
皿を重ねる。椅子を引く。ばん、と軽く布団をはたく。時おり、何かの機械の動力がうなる。
が、それは夜に吸い込まれていくようにだんだんと小さくなり、やがて粛々として消えていった。
二階には、リンクとゼルダだけが残された。
風は止んでいた。
波の音も、今はほとんど聞こえない。こうしていると、一段と寒さが身に染みた。
「もう少し、いいですか」
と、ゼルダが言った。
もっと星を見たいのだろうかと思ったが、いくら待っても、彼女が席を立つことはなかった。
そのかわりに、マントの袷からいたく控えめに、細い掌が伸びてきた。
引き寄せて握ると、ゼルダが肩に頭をもたせかけてきた。
甘えはじめのゼルダはいつも、その生まれにふさわしく慎ましやかだった。
「ロベリー、風邪を引かないといいですね」
「うん」
「リンクは、大丈夫ですか」
「うん」
「よかった」
ゼルダが笑うと耳元の毛にふわふわとした吐息がかかって、少しくすぐったかった。
リンクは顔を上げる。
雲が、空全体に広がりはじめていた。
星が一つ、また一つと隠れていく。
気が付けば、あたりはずいぶんと暗くなっている。それでも、ランプを付ける気にはならなかった。
うすものに包まれたように、青白い星の光はぼんやりと滲みはじめている。
かろうじてその存在は見つけられるが、もう輪郭も定かではない。
あの星で、百二十年。
その周りにある、見つけることすらかなわない星たちは、どれほど遠くにあるのだろう。
二百年、三百年。一千年、五千年。もしかしたら、一万年。
空の上は、いったいどこまで続いているのだろう。
ここに至るまでの長い長い旅の中には、迷ったものも、力尽きたものもいたはずだ。
針の先ほどの小さな小さな光だけが、今ここにたどり着き、リンクとゼルダの瞳を照らしている。
そしてまた、遥かなどこかへと向かっていく。
(途方もないな)
と、リンクは思う。
何て途方もないのだろう。星も、空も、時間も、人の運命も。
二十歳の姿をした百二十歳。
ふたたび成長しはじめた身体。
お伽話の勇者と姫巫女は役割を終え、姫君と騎士が帰るべき国はすでに亡い。
それでもリンクはここにいて、今この時を、ゼルダと一緒に生きている。
リンクは空いている方の腕を伸ばして、ゼルダを抱きしめた。
「リンク?」
聞こえないふりをして、細い首元に顔を埋める。
ほのかに林檎の香りがした。ぐりぐりと額を押し付けるたびに、それは甘く濃くなっていく。
ゼルダがここにいてくれる。
温かい身体を持って息をして、自分の名前を呼んでくれる。
甘えてくれる。甘えさせてくれる。
身を寄せあって、触れあって、旅をして夜空を眺めている。
そういった、ささいなことごとの全てが愛おしかった。
それは星々の欠片のように、リンクの腕の中でいつでもまばゆく輝いている。
「もう、休みますか」
ひそやかな恵みのように降りてくるゼルダの声に、リンクは首を横に振った。
「もうちょっと、このままがいい」
私も、とゼルダが言った。私ももう少し、このままがいいです。
小さな喉が上下に震える。
唇を押しあてると、その震えがもっとはっきりと伝わってきた。
何度もキスをする。喉、顎、頬。唇の外側は冷たくて、その分、内側は温かかった。
ゼルダはリンクの背に手を添えて、すべてのキスに応えてくれた。
夜中はひどく冷え込んだが、二人して潜り込んだベッドの中はとても温かく、快適だった。
厚地の布団となめらかな素肌に包まれて、リンクは明け方までよく眠った。
「本当は、手紙でオ教えするつもりだったんデスケドネ」
次の日、夫人がこっそりとリンクに教えてくれた。
「ドクトルが、”今の二人にとって、百二十は特別なナンバーだ”ッテ」
リンクは作業の手を止めた。
朝方、ついにゲストルームのドアが壊れた。
交換するには一度全部を取り外すしかなかったので、結構な仕事になった。
「やっぱり、ご存じだったんですね」
自分たちの年齢のこと。あまりにも出来すぎた偶然の一致。それが呼び覚ますだろう感情。
夫人がきゅっと目を細める。
「ドクトルは、ロマンチストだカラ」
外はひどい雨だった。
屋内にいても、遠くに近くに、雷が落ちる音が聞こえた。
ロベリーはゼルダをつかまえて、ここぞとばかりに講義をしている。
山のように積まれた資料や本を前にして、これはやりがいがありますね、とゼルダは目を輝かせていた。
海風でひどくやられていた蝶番を交換したので、ドアの開閉音はいたって静かなものになった。何度か開け閉めをして確認する。悪くない出来だった。
「オ仕事させちゃってスミマセン」
「いえ。次にお邪魔する時にも、使いますし」
リンクが言うと、オーキニ、と夫人は笑った。
二日後、今度は必ずシーカーストーンを持ってくると約束して、夫妻と別れた。
雨はどうにか止んで、雲間から夕日が顔を出していた。
望遠鏡の筒先で大きなガラスが光り、その横で、風車の羽根がぐるぐると景気よく回っていた。
遠くにかすむ水平線の上に、気の早い一番星が昇っていた。