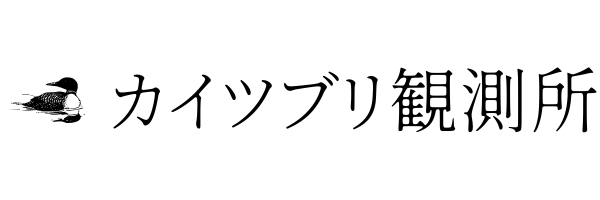アッカレ古代研究所はハイラル大陸の北東の、その突端にある。
もともとは灯台として使われていた。今でも”灯台”という方が、人々には通りがいい。
ハイラル王国がまだ健在だったころ、海岸線の守備と、近海に出る船の安全のために建てられた。
岬は小高い丘になっていて、あたり一帯の丘陵と海岸線とがいちどに見渡せる。
『大厄災』の日に起こった地震で、建物は半壊した。が、地面に落ちた灯芯とがれきの山とをかき分けて、そこに住み着いた人がいた。
アッカレ古代研究所の所長、ドクトル・ロベリーである。
彼は非常に優秀な研究者だ。専門は機械工学で、おもに古代に使われていた素材と、エネルギーの利活用を扱っている。
そしてまた、大変に壮健な人物である。齢百三十歳に届こうかという現在も、新しい発見を求めて、日々研究に邁進している。
そのロベリーから手紙がきた。先月のことだ。
――ユーたちに見せたいものがある。近々、研究所へ来てくれたまえ。ワイフと一緒に待っているぞ。
生成りの便せん一枚に、それだけ書かれていた。
そのあまりに簡潔な内容に、リンクとゼルダは思わず顔を見合わせた。
念のため封書も確認してみたが、それ以外のものは入っていなかった。達筆なハイラル文字で、”ハテノ村、リンクとゼルダの家”と表書きされていた。
「何か、重大な発見でもあったのでしょうか」
テーブルの向こうで、ゼルダが首を傾げた。
素朴な絵付けのティーカップから、ぼんやりと湯気が立っていた。
「どうかな」
リンクはペーパーナイフを鞘に納め、しっかりと留め金をかけた。どんなものであれ、ゼルダの前に刃物があるのは落ち着かなかった。
「そうならそうだってちゃんと書くと思うよ、ロベリーは」
「そうでしょうか」
「たぶんね」
ロベリーは個性的な人だが、真面目な人でもある。
本当の一大事ならはぐらかすことなく、きちんと説明をするはずだと、リンクは思った。
「とにかく行ってみよう。二週間もあれば十分だ」
ハテノ村は大陸の南東に位置している。対して、アッカレ古代研究所は北東の端だ。
かなり離れているが、リンクもゼルダも、旅には慣れている。
寄り道をしないでまっすぐに向かえば、それほど無理な行程でもなかった。
「そう、ですね……」
すぐには決めかねるというように、ゼルダは視線を彷徨わせた。
リンクは立ち上がってテーブルをぐるりと回り、その横に座った。
「嫌?」
身体を傾けて、ほっそりとした肩に頭をもたせかける。
顎の高さで切りそろえられた髪が、さやさやと頬に触れた。
こういうふうにすればゼルダはさほど拒みはしないというのを、リンクは最近覚えた。
甘え方にもこつがある。
ブラウスの襟からのぞく首筋から、なめらかな香りが漂っていた。
「色々とやりかけのものがあるので、それをどうしようかと。インパに送ってもらった史料の整理も途中ですし、前回の地質調査の取りまとめや考察も、まだまだ詰めたいところがあって」
「研究所は?」
「しばらく実験の予定はないので、大丈夫だと思います。プルアがへそを曲げなければいいですけど」
へそを曲げるプルアを想像して、リンクは笑った。
プルアはゼルダの勤め先であるところの、ハテノ古代研究所の所長だ。
仕事上の上役にあたるわけだが、いかんせん、彼女はゼルダに甘い。
自分たちをにこやかに送り出してはくれるだろうが、そのあとで、助手のシモン氏に盛大に当たり散らすのが目に浮かぶ。
シモン氏には悪いが、ここは我慢してもらうほかない。
「じゃあ、決まりってことで」
ね、とリンクがぐりぐりと頭を押し付けると、やめてください、とゼルダはむずがった。
もちろんやめるようなことはせず、そのままゆるゆると腰に手を回す。
性急には抱き寄せない。ゆるゆると、というのがこつだった。
実際ゼルダは、それ以上は嫌がるようなそぶりを見せなかった。
頬と頬とが重なる。目を閉じていても、彼女が笑っているのがよくわかった。
「リンクは、旅が好きですね」
「うん」
「――楽しみ、ですね」
「うん」
夕食の片づけはすっかり終わっていたので、それからあとはのんびりとしたものだった。
二人はいつも通り同じベッドに入って、いつも通り、一緒に夜を過ごした。
そんな甘やかな時間のことを思いだしつつ、リンクは目の前の棒を両手で握り直した。
金属で出来ているそれは、地面に水平方向に伸びている。
リンクが持っている部分はまっすぐだが、反対側の先端はコの字になっていて、それが大きな歯車にしっかりと噛んでいた。
よっ、と気合を入れて棒を押し込むと、ぎ、ぎ、と、いかにも大儀そうな音を立てて、歯車が動く。とても重い。およそ人の数倍はあるだろう自分の腕力でこの重さだ。
よくよく考えなくても、巨大な望遠鏡の台座なんて、人力で動かすようなものではない。しかも一人で。無茶がすぎる。
「動いてますヨー!もうチョット頑張ってー!」
底抜けに元気な指示が、見えないところから飛んでくる。
リンクはそれに返事はせず、棒を押し込むことだけを考えた。
燦々とした日差しが背中に降りそそいでいる。額に汗がにじんだ。
やっとのことで二歩進んだ時に、ふたたび大きな声が聞こえてきた。
「オッケーオッケー!バッチグー!そっち行きますネー!」
バッチグー、という言葉の意味はまったく分からなかったが、もういいとか大丈夫とか、そんなものだろうというあたりはついた。
リンクは棒から手を離し、周囲を見回した。
研究に不要なものは置かない、という所有者の意思を示すように、研究所の二階は、ものが少なかった。
小さな作業台、その上にある工具類、古びたランプ、金属製のオイル差し。
竹ぼうき、モップ、バケツ。壁際に、一人掛けのスツールがいくつか。作業時の足場として使われているのだろうか。手に取ってみると、表面に張られた布がけば立っていた。
そのうちの一つの表面をさっと払って、リンクは腰を下ろした。
あらためて眺めてみると、研究所は不思議な建物だった。
一階は平均的な石造りの住居だが、二階は吹き抜けになっている。
元は三階、いや四階まであったのかもしれないが、今は風化した壁があるだけだ。
崖下の海から風がひっきりなしに吹いてきて、屋根がわりに天井に張られた布がばたばたと揺れる。
雨や日差しを防ぐことを期待されているのだろうが、あまり効果はないのだろう。床板のあちこちが、日焼けや湿気で変色していた。
外壁には風車が取りつけられていて、大きな羽根が回っている。
古代エネルギーが使えない時のための動力源だそうだが、どのくらいの馬力が出るのかは疑問だった。ガーディアンを吊り上げているクレーンもある。残念ながら、動いているのを見たことはない。
建物をぐるりと廻る足場に沿うようには、見張り小屋兼ゲストルームが建っている。
鳥の巣箱のような形をしていて、日頃はろくに使わないからか、建てつけがきわめて悪い。
自分はまだしも、ゼルダをここに寝泊まりさせるわけにはいかないと、以前訪れた時にリンクが修繕した。
ドアがうるさく鳴るのを除けば、まあまあ過ごせるくらいにはなっている。
そういった諸々の中にあっても、やはり、望遠鏡の存在感は別格だった。
建物の中心を貫く柱の上に台座があり、そのさらに上に、望遠鏡は載っている。
金属質のぶ厚い胴が、太陽の光を浴びて、空へと一直線に伸びていた。
台座とそれに続く柱のあちこちに、大小さまざまの歯車がが嵌められている。
どれもみな望遠鏡と同じように、どっしりとした黒色をしていた。
以前は後ろの部分が外壁から乗り出していたが、どうも置き場所を変えたらしい。今は筒全体が、研究所の二階にすっぽりと収まっている。
そういえば、筒の先にあった休憩室——日傘と簡易ベッドが置かれていた。それだけ望遠鏡は大きく太い――も、撤去されている。
しばらく来ないうちに、色々なことが変わっていた。
「お疲れサマでシタ」
一階へと続く階段から、ジェリン夫人が顔を出した。
とんとんと軽快に階段を昇ってくる。
差し出された渋い色味の湯呑みをリンクが受け取ると、オ仕事させちゃってスミマセン、と夫人は言った。
「いつもは、古代エネルギーで動くモーターを使うんですケド。このあいだ、コレを前の方にズラした時に、パーン!とやっちゃッテ。いま修理チュウなのネ。出力設定は間違ってなかったハズなんですが、ま、よくあるコトデス」
特徴的なイントネーションに、あっけらかんとした明るさがあった。
まったく悪びれないところが、かえって清々しい。
「これで、なにかするんですか」
「それはお楽しみってヤツです。ダイジョーブ、今夜には分かりますヨ」
「はあ」
重労働の対価は、もうしばらくはお預けらしい。
リンクは湯呑みを傾けた。茶はちょうどいい温度に冷まされていて、あっさりとした飲み口だった。
失礼シマス、と断って、夫人は作業台へと足を向けた。
「ドクトル、とても楽しそう」
夫であるロベリーをドクトル、と呼ぶのは、出会ったころからの習慣らしい。
彼女はかつて優秀な助手としてここにやってきたのだと、以前ロベリーに聞いた。
そのロベリーとゼルダは今、一階で研究談議の真っ最中だ。
ミナッカレを発って二日。
昨晩宿泊したヒガッカレ馬宿を遅くに出て、研究所の戸を叩いたのは昼過ぎだった。
それからもう二時間ほどは経過したはずだが、話の種は尽きないようだ。
――ソウタイクッセツリツ、ヒセンケイコウガク、キンセキガイブンコウホウ。
もはや綴りすら想像できないような言葉が、さまざまな機械音と一緒になって、時おり下から聞こえてきた。
「朋あり遠方より来たるまた楽しからずや、デスネ」
トモアリエンポウヨリキタル。
リンクは頭の中で繰り返してみる。
「……新手のまじないですか」
「そんなモンです。シーカー族のいにしえの叡智、スバラシイデスネ」
夫人の背中は、どこか誇らしげだった。
特徴的な服装と装飾品。いで立ちはシーカー族そのものだが、結い上げた髪はうすい金色をしている。
彼女は生粋のハイリア人だった。
「ドクトルにはもう、あまりトモダチがいないカラ」
夫人はランプを持ち上げて、底の燃料皿を取りはずした。
中身をこぼさないように、慎重な手つきでオイル差しの口を傾ける。
よほど使い古しているのだろうか。持ち手の金属が、指のかたちに沿ってへこんでいた。
「シーカー族はゴ長寿の方が多いデスし、ときどき手紙のやりとりをするヒトはいるけれど。それでももう皆、こんなトコロまで来ることはできないのネ。ドクトルも、ここを離れるのはチョットきびしいお歳だから。あなたがたが来てくれて、とても嬉しいのだと思いマスヨ。……本当にありがとう。オーキニ」
「……いえ」
リンクはどう答えてよいのか分からず、迷ったあとで、残った茶を一気に飲みほした。舌の上に、茶葉の欠片がひっついた。
望遠鏡と壁と布のあいだから、青空が覗いている。
アッカレは荒れた天気が多い印象だったが、それは思い込みだったのかもしれない。
あまり長居をしたことがなかったので、気がつかなかっただけなのだろう。
我関せずというように、風車は回っている。
羽から長い影が伸びてきて、床板に黒い線が現れては消えていった。
「さ、これでヨシ」
腰の手ぬぐいでオイルの残りを拭き取りながら、夫人が戻ってくる。さっぱりとした表情だった。
「ところで、リンクサン。グラネットには最近オ会いになりまシタ?」
いいえ、とリンクは答えた。
そういえば、しばらく会っていない。
グラネットは、ロベリーと夫人の一人息子だ。
両親の研究のうち、特に材料に興味をもったらしい。古代技術を使った希少な防具を研究するために、現在は修行の旅に出ている。
歳はリンクよりやや年嵩くらいだ。
かつての旅の間に、何度か世話になったことがある。
「まったく、ドコにいるのやら」
「イチカラ村じゃないんですか? 」
夫人は首を振った。
「こないだ、ゲルドのバザールから手紙がきマシタ。その前はタバンタの山奥から」
「気になりますか」
「旅に出したのはコッチですから、生きててくれればってなモンですケドネ。あの子ももういい歳デスし、自分でドーにかしてるデショウ」
いい歳。
それは、どのくらいを年齢を指すのだろうう。
一応二十歳ということにしてはいるが、リンクの実年齢は百二十歳で、明確な記憶のもとに生きているのは、そのうち直近の三年だ。
世間並にいえば、自分はいったい何歳に相当するのだろう。
あと何年生きれば自分は、いい歳、になるのだろう。
「ワタシがここに来たのもアレくらいでした。時間が経つのは早いネー」
「おいくつだったんですか」
アラ、と夫人は目をきゅっと細めた。
「女性に歳を聞くのはタブーですヨ」
「いえあの、そういう意味じゃないんですけど」
慌てて弁明すると、夫人の目はますますもって細くなる。そうすると、目尻に引いたあざやかな青がはっきりと見えた。
いいデショウ、今日はトクベツ。夫人は笑った。
「ドクトルが初めてワタシをワイフと呼んだのは、三十年以上前デスネ。あの子が生まれたのは、それからわりとスグ。だからまあ、ソノくらいの歳デス。ソリャもう、イロイロとありましたけどネ。過ぎてしまえば、時間なんてアッという間。光陰矢の如し、歓を得ては当に楽しみを作すべし」
「コウイン、ヤ、……え?」
「新手のオまじないデスヨ、オまじない」
夫人は意味深げにそう言いおいて、くるりとリンクに背を向ける。
散乱していたスツールをひとところにまとめ、竹ぼうきとモップを揃え、その隣にバケツを寄せる。
その間、夫人は歌うように繰り返し口ずさんだ。コウイウンヤノゴトシ、カンヲエテハマサニタノシミヲナスベシ。
「俺にも分かる言葉でお願いします」
「今がイチバン、ってことデス」
絶対に違うのだろうと知りつつ、リンクも音だけをなぞってみる。
コウインヤノゴトシ。カンヲエテハマ、云々。
どんなに唱えてみても、それになにがしかの効用があるとは思えなかった。
夫人は去り際、夕食のメインディッシュの味付けを聞いてきた。塩、もしくはソイソース。ゼルダは塩が好きだと伝えると、夫人はリョーカイデス、と言って、人差し指と親指とで円を作った。
階段を下っていく足音を聞きながら、リンクはふと、三十年くらい前のこの研究所はどんなものだったのだろう、と思った。
九十歳を超えていたロベリー。
ハイリア人でありながら単身ここを訪れた、若い娘だった夫人。
いい歳の息子は、まだ生まれてもいない。
空になった湯呑みを手持ちぶさたに揺らしながら、リンクはしばらくそこに座っていた。
崩れかけの壁の向こうから、強い日差しがまっすぐに差し込んでいた。
夕食には、まだ時間がありそうだった。