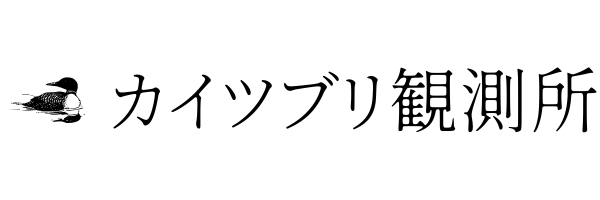120光年の旅
宿帳にサインをし終えたところで、カウンターごしに声をかけられた。
「いい時間に来たよ。今なら、まだベッドを選べる」
「そうなんですか」
と、リンクは答えた。
「ありがたいことだけどね。お客さんが多い日には、私たちのを使ってもらうなんてこともあるよ」
「じゃあ、皆さんは?」
「姉妹で仲良く雑魚寝」
ジュンはおかしそうに肩を竦めた。
言うほど嫌ではないのだろう。笑うと、くっきりとした一本線の眉毛がぐっと上がる。
「今度、新しい幔幕を張ることにしたんだ。ちょっと前までは、うちには人が来ないから馬もいない、馬宿じゃなくて羊宿だ、なんて姉さんが言ってたのが嘘みたいだよ。手が足りなくて、姉さんは案内係で出ずっぱり。僕も花畑の世話係を返上して、こうやって番頭の真似ごとをしてる」
「花畑は、今は」
「下のツユの担当」
インク滲みを防ぐための紙を添えたあと、手慣れた様子で宿帳を閉じる。
カウンターに置かれた二人分の宿泊代金を丁寧に数えて、確かに、と頷いた。
「”ミナッカレには何もないけど、風景は特別にいい”って、評判みたい。わざわざ、平原の向こうから来てくれるお客さんもいるんだ。最近は特に恋人とか、ご夫婦連れも多いよ」
さらりとした言い方に、含むところは感じられなかった。
だからリンクも、そうですか、とだけ答えて流した。
開け放たれた入り口から、涼やかな風がはいり込む。それと一緒に、真赤に色づいた枯れ葉が一枚、リンクの目の前に落ちてきた。指の腹でカウンターに押し付けると、かさりと乾いた音がした。
「やっぱり観光で?」
「いえ。北東の岬の、灯台まで。友人に会いに」
「そう。素晴らしいな」
「素晴らしい、ですか」
楽しい、とか素敵、というなら理解できるような気がしたが、素晴らしい、というのはちょっと意外だった。
「そうだろう。友人に会うってだけで遠出ができるなんて、素晴らしいことだよ。少し前までは、旅ってもっと物騒で、命がけだったじゃないか」
そこはお客さんのほうが詳しいか。ジュンは笑う。
「魔物が急に減りだしたのが、確か、一昨年のなかばくらいか。たかだか一年か二年だっていうのに、世の中ってずいぶんと変わるものだね。ここに来る人の顔つきも変わったよ。もちろん、すごくいい意味で」
幾人かの女性の声が、幔幕の向こうに聞こえる。
ジュンの姉も混じっているかもしれない。声はにぎやかに笑いさざめきながら、だんだんと遠ざかっていった。
確かに以前にはなかった空気だなと、リンクは思う。
かつてリンクが一人でハイラル中を駆け回っていたころ、旅にはもっと、剣呑な意味あいが混じっていた。
約百年前に起こった”大厄災”。
その後ハイラル全土にはびこった魔物の存在は大きく、道中は常に危険だった。旅人のほとんどは向こう見ずか命知らず――言うまでもなくリンクもそうだった――で、たいていは、一人で行動していた。
しかし、自宅からここに着くまでの数日間、あちこちで見た旅人たちの様子は違っていた。
もちろん遠出につきものの緊張感は持っているが、すれ違いざまに掛け合う声は、ひとしく明るかった。女性が以前よりも増えて、多人数で連れ合うのもめずらしくない。
旅はかつてよりもずっと、簡単で気軽なものになりつつある。
ふたたび風が吹いてきた。
湿り気の少ない、心地よい風だった。
「涼しいですね」
「もうちょっとしたら、ストーブの出番かな。岬の方は、もっと季節が進んでいると思うよ」
え、と思わず声が出る。
「そんなに冷えますか」
「日中はそんなでもないけど、夜はね。毛布も余分に出しておかないと」
忙しいなあとジュンがつぶやいたとき、おぉい、お客さんだぞぉ、という、間延びした男の声がした。
彼女たちの父親だろうか。馬のいななきが二頭分、それに重なる。
「はい、ただいま」
ジュンは外の様子を確かめてからカウンターに戻り、宿帳をすばやく開く。
「ごめん。次が来たみたいだ」
「いいえ」
ごめんもなにもない。長々と居座っていたのはリンクの方だった。足元に置いたままの荷袋の紐を引っ張り上げる。
「奥の二つ、使います」
「どうぞ。食事はパンとスープはサービス、あとは各自で適当に。外の料理鍋は、ほかのお客さんと譲り合って使ってくれ。お連れさんにも説明しておいてくれると助かる」
リンクは軽く手を挙げて応え、カウンターをあとにした。
並んで空いているベッドを選んで、それぞれの脇に荷袋を置く。
四隅をそろえて畳まれた枕カバーとシーツが、ベッドの上に載っている。お揃いの馬の刺繍が愛らしかった。
そうしている間にも、新しい客が宿に入ってくる。
いらっしゃいませ。ミナッカレ馬宿にようこそ。
お決まりの定型句だが、ジュンが言うと不思議とさわやかだった。よく通る、いい声だ。案外こういったところに、繁盛の秘密が隠されているのかもしれない。
幔幕の外に出ると、そろそろ日が傾こうという時間になっていた。
そこらにあるもの全体が、赤っぽく変色しはじめていた濃く色づいた葉と、木々の枝。見上げるほどに高い岩山の硬い表面と、その頂上にある、アッカレ砦の残骸たち。
街道にほど近い大きな木の下で、ゼルダがしゃがみ込んでいる。
女の子と一緒だ。顔つきや服装を見るに、”下のツユ”だろう。以前見たときよりも、体がひと回り大きくなっている気がする。
ゼルダは手に持った小枝を筆代わりにして、地面に何ごとかを書きつけている。
ツユは前のめりになってそれを覗きこみながら、ときどき感心したように、ふむふむと頷いた。
そういえば、ツユにトンボを見せろとせがまれたことがある。ゼルダも生き物が好きだから、通じあうところがあるのだろう。
「ゼルダ」
声をかけると、ゼルダはぱっと顔を上げた。
ツユに丁寧にお辞儀をして立ちあがり、小走りにこちらに向かってくる。身体のあちこちに、枯れ葉がくっついていた。
「もういいの?」
「はい。ツユさんのお仕事に割り込んでしまったのは、私ですから」
「ちょっと待ってて」
言いながらリンクは、寄ってきたゼルダの頭や肩を、優しくはたいた。
髪の毛やマントの繊維に引っかかっていた葉が、面白いくらいに落ちていく。
ゼルダはくすぐったそうに身をよじったが、リンクは知らないふりをした。
やがてすっかり元通りになると、ゼルダはありがとう、と微笑んだ。
どういたしまして、と言うかわりに、リンクはゼルダの手を取った。そのまま並んで歩きだす。
「裏の牧場から、アッカレ海が見えるよ。まだ明るいから、イチカラ村とか、マキューズ海岸あたりもいけるかも」
「古代研究所は見えるでしょうか」
「どうかな。けっこう遠いし」
頭の中で地図を広げる。
全体的に平らかで景色に変化がないから分かりにくいが、アッカレ地方は広大だ。
研究所は、その際の際にある。肉眼で確認できるかどうかは難しいところだった。
「ロベリーは元気かしら」
と、ゼルダは言った。
「三日後にはわかるよ」
「それもそうですね」
日はどんどんと落ちていく。
絡められた細い指先は、心なしか冷たかった。
やっぱり夜は冷えるんだな、と思いながら、リンクは手の中におさまった温かさを大切に包んだ。