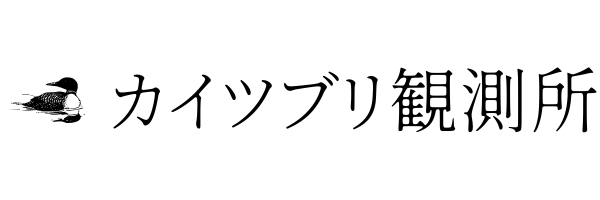香り高くほろ苦い
ごちそうさまでしたと言って、ゼルダは微笑んだ。両手に包んだカップをくるりと回す。
ここが屋外で、ほこりっぽい馬宿で、ごちゃごちゃと荷物を置いた炊事場だということを忘れるくらい、美しい所作だった。
「少し苦みが強いですが、悪くはない思います。付け加えるとするなら、ミルクを入れてみてはどうでしょう。苦味が緩和されて、口当たりが良くなるかと」
「なるほど。いや、参考になります」
男はひたすら恐縮するように頭を下げて、ゼルダからカップを受け取った。
目の前のやり取りを眺めながら、リンクはひと口、自分に用意された分のその飲み物を啜る。
たしかに苦い。かすかな酸味もある。しかし同時に、なんとも表現しがたい、独特の香ばしい匂いがした。
基本的に、心地よい香りというのはうま味と一緒にやってくる。だからこの感じは、かなり独特だ。
「わたしは、先に幕のほうに戻りますね。リンクはゆっくりしてください」
失礼いたします、と丁寧にお辞儀をして、ゼルダは母屋の方に歩いていった。
そのなだらかな後ろ姿が完全に見えなくなったあと、男は盛大にため息をついた。調理に使った小鍋やらすりこぎやらを、すごすごと片付けはじめる。
「失敗だったかなあ。……目が笑ってなかった」
「気のせいだと思うよ。ゼルダはいつでも真面目だから」
「だといいんだけど」
男はがくりと肩を落とす。
「これでも、ずいぶん改良したんだよ。聞いてくれるか、ここに至るまでの苦労の物語を」
あまり長くなるのはちょっと、とは思ったが、リンクは結局、男の話を聞いてやることにした。
宮廷料理の再現に心血をそそぐこの男は、その情熱の向かう先が少し変わっているだけで、いたって善良で気さくな人物だ。かつての旅の縁もある。こうして試作品を無償で賞味させてもらっている以上、与太話くらいは付き合ってやるのが義理というものだ。
何よりリンクのカップには、まだ飲み切っていないそれが残っていた。
男は続ける。
「大厄災が起きる前の、特に城下町で好まれた飲み物なんだ。あちこちの文献に登場するんだが、なにせ地方では作られなかったせいで、再現ができなくてね。幻の逸品になっていたんだ。で、このあいだ他のお客さんが持ち込んできたのが、まさにその製法の本だった、ってわけさ。感動したよ。涙が出た。原料の豆の産地から栽培方法、もちろん美味しい淹れ方までもがばっちりと。これはもう、女神さまのおぼし召しだとね。それでこの馬宿の名物にすべく、目下格闘中というわけなんだけども」
そこまで言って男は、ずい、とリンクににじり寄った。
「君の、正直な意見を聞きたい。どう思う、この、コーヒーを」
聞いて、ああ、とリンクは思い出した。
――そうだ、これは。
「コーヒーって言うんだっけ」
「……聞いてるのはそこじゃないんだが」
ごめんごめん。笑いながら、リンクはふたたびカップを傾ける。
口に含んだとたんに押し寄せる、圧倒的な苦さ。と同時に、嗅覚を惹きつけてやまない魅惑的な香り。
ああ、そうだ。あの時もそうだった。
――坊ちゃんには、まだ早いか。
そう言ったのは誰だったのか。思い出せない。
ぼんやりと浮かび上がる風景はうす暗く、しかし温かい肌触りがした。
幾人もの大人たちと一緒になって、焚火の周りを囲んでいる。皆、ハイラル王国の兵士の鎧を身に着けている。
談笑。誰だ、子どもにコーヒーを飲ませたのは。
――私だよ。
すぐ近くから、低く穏やかな声がする。
――父さんと同じものがいいと、この子が言ったのでね。
自分は少しだけむっとした。
たぶん、こんな風に反論した。大人はこんなものが美味しいの? 肉とか、お菓子じゃなくて。
――そういう美味しさとは、ちょっと違うんだ。君も、大人になれば分かるよ。
頭をわしわしと撫でられる感触がする。くすぐったさと気持ちよさと、ちょっとの気恥しさ。父さんは、いくつになっても自分を子ども扱いした。
――大人になったら? おっきくなって、強くなって、父さんみたいな騎士になったら?
――大きく出たなあ、坊ちゃん。
ふたたび談笑。今度は父さんも加わった。なんだよもう、と膨れ顔になる。一層大きくなる笑い声。
焚火が威勢よく爆ぜる。どんな場面だったのだろう。いつの夜のことだったのだろう。
そこから先のことは、まるで霧に包まれた森の中のように何も見えず、やがてふっと掻き消えた。
すっかり冷めたコーヒーは、苦みに加えて酸味が増していた。
顔を思い出すことすらできない父親への申し訳なさとともに、口内に残るそれをゆっくりと嚙みしめる。
命を繋ぐために眠りについた百年の間に、リンクは記憶を失った。
それらは目覚めて三年経った今でもほとんど戻っていないが、ある瞬間、思いもしないきっかけで甦ることがある。
目に映る景色。風の音。指の感覚。舌に載る味。鼻孔を通りすぎてゆく香り。
不思議なもので、言葉や文字で訴えかけられるよりもずっと、そういうもののほうが思い出す契機になりやすい。
そしてそれは、どうやら自分だけに限ったことではないということを、リンクは最近知った。
「ごちそうさま」
リンクは最後のひと口を飲み干したあと、立ち上がった。
ゼルダの側にいよう、と思った。
ゼルダはリンクとは違う。たくさんの思い出を抱えたまま、百年の時を超えた。
大厄災で滅びた王国の姫君として生きた時間は、彼女の中で未だ息づいている。
ミルク入りのコーヒーをともに楽しんだ相手のことだって、鮮明に覚えているに違いない。
ゼルダは何か話すだろうか。彼ら彼女らにもう会えないことを嘆くのだろうか。それとも、ただ黙って、少し悲しそうな顔で笑うのだろうか。
どれでもいい、とリンクは思った。
思い出をどう味わうかは、人それぞれに違っていて、どれが正解というわけでもない。
ただきっと、ゼルダはこういうとき、誰かと一緒にいたほうが楽になる。はっきりと聞いたわけではないけれど、恋人として過ごしていると、そういう感覚は自然と掴めてくる。
「で、どうなんだい。これの味は」
「そうだな」
なおも食い下がる男に向かって、リンクは言った。
「嫌いじゃないよ。香りがいいし、変わった風味も、慣れれば癖になる。案外、好きになる人は多いと思う。十分売り物になるよ」
でも、とリンクは付け足した。
「俺は、たまにでいいかな」
不思議そうな顔をしている男に手を挙げて、リンクはその場をあとにした。
苦みも酸味も芳香も、すでに身体の中からすっかり抜けていた。なんて儚い。だからこそ無性に恋しくなるけれど、追いかけたところですぐに消えてしまう。
ここを訪れるいっときにだけ楽しむくらいが、自分にはきっと、ちょうどいい。
そんなことを思いながら、リンクはゼルダの元へと歩き出した。
〈了〉