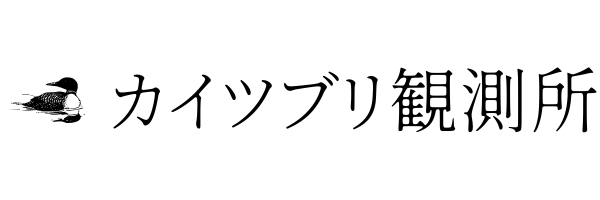彼女の王国
ハテノ村の家に一緒に住むようになったあと、ゼルダは庭に植物を植えはじめた。
種類は多様だった。
庭造りの定番であろうあざやかな花ばかりではなく、傍目には雑草にしか見えないものも、中にはあった。
すべての植物はその特徴に合わせて、植わる場所が決まっていた。
この花は日当たりのいい西側に。あの草は水辺に。これはもとは乾燥地帯に自生する品種だから、岩場の近くのほうがいいでしょう。
そう言って、ゼルダはきちんと区分けをした。
水まきをするための道も整備した。
これにはずいぶんと時間がかかった。持って生まれた凝り性な気質は、半端なものを許さなかった。効率的かつ景観を損なわないものをと、さまざまに工夫を凝らした。
その甲斐あってか、庭はいつしか、ひとつの生活圏を成すまでに成長した。
同種のものがゆるやかな集団をつくり、それぞれの領分にしっかりと根を張って、奪くことなく争うことなく、他の集団とともに共存していた。
彼女の手がつくりだした小さな王国は、おだやかで、慈しみにあふれたものだった。
もちろん、それが永遠に続いたわけではない。
嵐が来れば、草は折れて芽は流された。
反対に、雨が降らなければ根は枯れた。
もっとも被害が大きかったのは、ひどい霜が降りたときだったろうか。
庭一面が白く細かな氷で覆われて、王国は一夜にして廃墟と化した。
死の気配が地面の上に濃く漂い、息の詰まるような静寂が横たわっていた。
気候がよく、どの種も順調に育った年だっただけに、その惨状は目を覆いたくなるようなものがあった。
「自然は残酷なものですから」
息絶えてぐったりと横たわる花を引き抜きながら、ゼルダは言った。
「でも、すべてが終わったわけではないもの」
かろうじて生き延びたわずかな種をひとところにまとめたあと、ゼルダは大きな穴を掘った。
そこに夥しい数の死骸を埋めたあと、土を盛って丁寧に均した。
次の春、その上にまた新しい国をつくった。
豊かな養分が功を奏したのか、そこからは寒さや虫に強い品種がたくさん生まれた。
ゼルダは何度でも繰り返した。心をこめて育てた命たちがなすすべもなく斃れるたびに、打ちひしがれて傷つきながら、それでも次代へと継ごうとする手を止めなかった。
植物にとって彼女は、英明で、ときに果断な君主であるのと同時に、慈悲深い守り神だった。
彼女の王国はいまもこの場所で、繁栄を続けている。
〈了〉