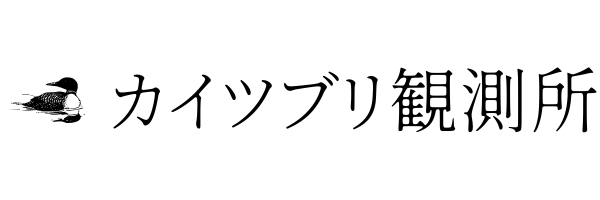ポリグラフ
その日の食卓の話題はもっぱら、プルア女史の新しい発明品のことだった。
「嘘発見器?」
川魚のムニエルにナイフを入れながら、リンクは聞いた。対面に座るゼルダが頷く。
「いつも思うのですが、プルアのネーミングは安直すぎます。シーカーストーンもそうでした」
「分かりやすくていいと思うけど」
「……リンクはプルアと感性が似ていますね」
「褒められてるのかな、それ」
「もちろん」
いまいち釈然としないものを感じつつ、リンクはもごもごと口を動かした。
丁寧に骨が抜いてある身は柔らかく、塩と胡椒の加減もちょうどいい。
「これ美味しい」
「ありがとう」
ゼルダはにこりと笑った。
彼女の旺盛な探求心は、近頃は料理に向けられている。この間までは妙に凝ったものが多かったが、そういうものに価値を置く時期は過ぎたらしい。
シンプルかつ滋味のある品に回帰していた。
「プルアったら、”せっかくだから剣士クンにやらせよう”なんて言ったんですよ。”アイツにだって嘘のひとつやふたつ、絶対にあるワヨ”って。もちろん、丁重にお断りしましたけれど」
「それはどうも」
ありがとう、の意をこめて、リンクはゼルダのグラスに水を注ぐ。
女史が非常に優秀な科学者であり、得難い友人でもあることは確かだが、進んでその先鋭的な実験の対象になりたいかといえば、答えは否だ。
「もの自体はよく出来ているんですよ。被験者の、ちょうどこのあたりに器具を付けて」
ゼルダは手のひらをリンクに見せた。
その真ん中と、薄い皮膚の張った手首とを指で示す。
「実験者が用意した質問に答えてもらいます。そこで発生する生体反応を器具が計測して、嘘かどうかを判断する。要は、被験者がどのくらい心理的な負担を覚えているかを調べるんです。そういうときの身体って、わたしたちが思っている以上に正直なんですよ。動悸がしたり汗をかいたり、呼吸が早まったり。リンクにだって、経験はあるでしょう?」
「そう言われれば、まあ」
覚えているだけの人生でリンクがもっともそれを感じたのは、おそらく彼女に対してこの家に一緒に住まないかと申し出た時だった――驚くべきことに、世界を滅ぼさんとする厄災に対峙した時よりも酷かった――が、本人を目の前にして言うものでもないので、リンクは別のことを聞いた。
「そんなに外に出るものかな」
ええ、と、ゼルダは言った。
「私は見慣れているので、結構はっきり分かりますよ。ああ、息が浅くなっているなとか、指先がこわばっているなとか。あの頃の城にはいつも、そういう人がたくさんいましたから」
そっか、とリンクは答えた。
あの頃、つまり百年前のことを、リンクもゼルダもさらりと流せるようになった。
感性が成熟したのか、はたまた鈍化したのか。判断は難しいところだが、流れ続ける時間の中で、お互いがお互いなりに変化していることだけは確かだった。
冷めてきたスープを丁寧に掬う。
ミルク仕立てのそれはまぶしいほどに白く、舌触りがなめらかだった。よほど長いこと煮込んだらしく、具材のほとんどが溶けて小さくなっていた。
ボウルの底に残った最後の一滴を、綺麗にさらって喉に流し込む。
「そんな器具を付けられたら、嘘とか関係なく緊張しそう」
「プルアもそこは問題だと言っていました。それとなく装着できる環境をどうやって用意するかと……」
「そっちのほうが難問じゃない?」
確かに、とゼルダは首を傾けた。
「もう少し工夫が必要ですね」
そうして次々と披露される嘘発見器の改善案に相づちを打っているうちに、ムニエルも付け合わせのピクルスもスライスされたパンも、着実に皿の上から消えていった。
リンクはよく食べたし、ゼルダはよく喋った。
「今日の料理はいかがでしたか」
洗いざらしのふきんで皿を拭きながら、ゼルダが聞いてきた。
食器を棚に戻す手を止めて、リンクは振り向く。
「そうだな……。ムニエルはあのくらい淡白なほうが好きだし、スープもよく味が出てて美味しかったよ。でも」
「でも?」
ぎゅっと皿の縁を握るゼルダの目は真剣だ。だからリンクも茶化さずに、神妙な面持ちで答えた。
「スープの具は、もう少し大きいほうがいいかな。食べ応えもあるし」
「ああ!」
ぱっと、ゼルダの表情が明るいものに変わる。
「細かいほうが消化に良いかと思ったのですが、なるほど、食感や満足感も大事ですよね。リンクの指摘はいつも具体的で、とても助かります。他にも気がついたことがあったら、すぐに言ってくださいね」
弾むような口ぶりで言ったあと、ゼルダはまた皿を拭きはじめた。鼻歌まじりでご機嫌だ。
リンクもまた棚に向き直る。そしてこっそりと、己の手のひらを見つめた。
汗は滲んでいない。
その手を胸にあててみる。脈拍は正常。肺の動きはいつもと変わらず、呼吸も安定している。
リンクはなんだかおかしくなった。
自分は案外、詐欺師の才能があるのかもしれない。
「鍋、外で洗ってくるよ」
手つかずのまま調理台に載っていた寸胴鍋を、取っ手を掴んで持ち上げる。満面の笑顔のゼルダを背にして、リンクは表に出た。
ところどころに鱗のような雲が広がる夜空に、月が浮かんでいた。
裏手の土間にしゃがみこみ、汲み置きの水で洗い流す。軽く上下に振って水を切ると、鈍色の鍋肌をつたう滴が月明りを反射して、ぴかぴかと輝いた。
リンクは先ほどの会話を、頭の中で繰り返す。
――スープの具は、もう少し大きいほうがいいかな。
あれは、嘘だ。
スープに入っている野菜の切り方など、本当はどうでもいい。
もっと極端なことをいえば、料理の味などどうでもいい。
凝っていようが簡素だろうが、飯は飯以上でも以下でもない。
もちろん美味いにこしたことはないし、口にしやすいように加工してもらえると助かる。
しかし、本音はどうなんだと詰め寄られたら、なんでも一緒だとリンクは答える――ゼルダ以外には。
秘密なり偽りがあり、それを隠して、そ知らぬ顔を決め込む。
世間一般の嘘の定義からすれば、目的がどうあれ、これもれっきとした嘘になる。
恋人に嘘をつくなんてよくないことだと、世の人は思うのかもしれない。
お互いの間には揺るぐことのない真実だけがあり、それは曇りなく透き通ったものであるべきだと。
でもリンクは、少しだけ違うことを考えている。
事実はただ事実であるだけで、それがあらゆる意味にも価値にも勝るということはないと、リンクは思う。
目に見えるもののすべてが本当である必要などないし、なにもかもを明け透けに語ることが、幸福の絶対条件であるとも信じていない。
リンクにとって意味があり価値があるのは、ゼルダの幸せだけだった。
それをわずかにでも損なう可能性があるならば、リンクの食への価値観、なかんずくスープの具材についての真実性なんて、それこそ、煮込まれてぐずぐずに溶けて、色も形もなくなってしまった玉ねぎほどの価値もない。
腹に入れれば、真実も嘘もみな一緒だ。時間をかけて消化され、吸収されて、やがて誰の目にも分からなくなる。
プルアの例の発明が万が一にも改良されたら、それは微量の汗として、わずかな体温の上昇として、吐息にまぎれこむ不純物として計測されて、見つかってしまうのかもしれない。
しかし来るかどうかもわからないその日までは、リンクはこんなふうにして、大きな幸せとささやかな嘘とを一緒くたにしながら味わっていたかった。
「リンク? お鍋、大丈夫ですか」
戸板がうすく開いて、ゼルダが顔を出した。
暗がりの中にあっても、その姿はよく見えた。
室内から漏れ出る光が金色の髪にあたって、彼女の周りだけが、いくぶん明るくなっている。
「すぐ行く」
リンクは笑って手を振った。
鍋を抱えて向き直り、家へ向かって歩いていく。
春の終わりに似つかわしい、あたたかな風がそよぐ夜のことだった。
〈了〉